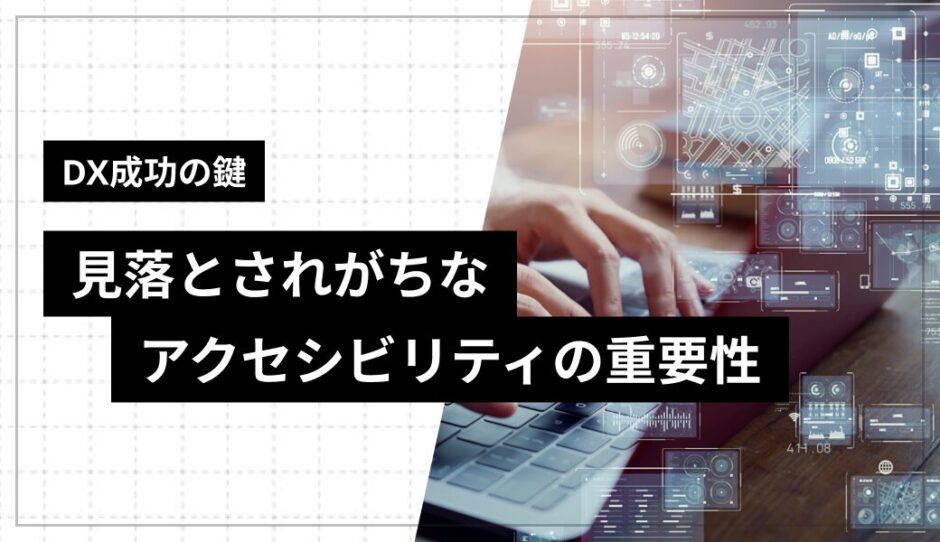近年、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組んでいますが、その過程で見落とされがちな重要な要素があります。それが「アクセシビリティ」です。IMD世界デジタル競争力ランキング2024によれば、日本は67カ国中31位と、主要先進国の中では低迷しています。特に「デジタル・技術スキル」「機会と脅威を把握する力」「企業の機敏性」の項目で最下位の67位に位置し、デジタル人材の不足やデジタル変革への対応力の弱さが浮き彫りになっています。
本来のDXとは、単なるシステム刷新や業務効率化だけではなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルを変革し、新たな価値を創造することです。その価値創造には「誰もが使える」というアクセシビリティの視点が不可欠です。高齢者や障がい者を含むすべての人々がデジタルサービスを利用できなければ、真の意味での社会変革は実現できず、企業も大きなビジネスチャンスを逃してしまうでしょう。
では、日本企業はどのようにしてこの課題に対応すべきでしょうか。本記事では、世界のリーダー国の成功事例から日本の課題を分析し、DX推進にアクセシビリティを統合するための具体的なアクションプランを提案します。
世界のリーダー国におけるDX推進とアクセシビリティ戦略
世界の主要なDX推進国では、デジタル変革とアクセシビリティを一体のものとして取り組む動きが顕著です。以下では、包括的なデジタル社会の実現を目指す各国の成功事例と具体的な施策を紹介し、アクセシビリティ対応がビジネス成果にどうつながるかを示します。
米国では連邦・州レベルで、DX推進とアクセシビリティの両立が図られています。具体的には、ADA法(Americans with Disabilities Act:障がい者の権利保障法)やSection 508(リハビリテーション法508条:政府機関が調達する情報技術のアクセシビリティ要件)により、Webサイトやデジタルサービスのアクセシビリティ対応が強く求められています。2024年には全米で4,000件超のADA関連訴訟が提起されるなど法的リスクも顕在化していますが、米国企業はアクセシビリティへの取り組みを単なる法律対応だけの問題ではなく、ビジネスチャンスと捉えています。全米に6,100万人以上存在する障がい者という消費者層へのリーチを拡大することで、新たな市場の開拓につながるからです。
特筆すべきは、業界横断の取り組みです。「Teach Access」は教育機関・テクノロジー企業・障がい者支援団体が協力して設立された非営利団体で、将来の技術者教育にアクセシビリティを組み込む活動を行っています(注釈[1])。これには米Microsoft社、米Google社などの企業も参加し、アクセシビリティ教育の普及に貢献しています。また、年間1000万ドル以上のアクセシビリティ研究開発投資を行う企業も少なくなく、大学との産学連携によるイノベーションも盛んです。こうした企業主導の取り組みが「ユニバーサルデザイン」文化を醸成し、米国のデジタル製品が国際市場でも競争優位を確立している要因となっています。
シンガポールは「スマート国家(Smart Nation)」戦略のもと、デジタル政府と包括的なサービス提供を推進しており、アクセシビリティ施策にも先進的に取り組んでいます。政府はデジタルサービス基準(DSS)を策定し、高齢者や障がい者を含むすべての国民が利用できるユーザーフレンドリーなサービスを目指しています。2025年にはデジタル発展省(MDDI)がこのDSSを強化し、各行政機関がWCAG準拠のサービス設計を行えるよう、コントラスト比チェックツールの活用や障がい当事者によるユーザーテストの徹底など、具体的なガイダンスを拡充すると発表しました(注釈[2])。
また、政府設立の障がい者支援機関「SG Enable(シンガポール・イネーブル)」と連携して障がい者のデジタルスキル向上と雇用創出も進められています。こうした取り組みにより、シンガポールは電子政府ランキングで世界3位(2024年)を達成し、「誰一人取り残さない」デジタル施策が高い行政サービス利用率と企業の競争力強化に寄与しています。
デンマークは統合デジタル戦略2022-2025で、「デジタル社会への包摂(デジタル・インクルージョン)」を重点課題に掲げ、市民や企業が行政サービスに平等にアクセスできる環境を整備しています(注釈[3])。具体的には、高齢者等に代わって電子申請できる代理人制度や、誰でも使いやすいユーザーインターフェースの採用など、アクセシビリティを考慮した施策を導入しています。その結果、行政の効率化だけでなく国全体のデジタル成熟度が向上し、国際的な電子政府ランキングで3期連続世界1位を達成しました。企業にとっても、アクセシブルなデジタルサービスを提供できる環境が整ったことで、より幅広い人材活用や新規顧客の開拓が可能になるなどビジネス上のメリットも生まれています。
ドイツはEU最大の経済大国として、EAA(European Accessibility Act:欧州アクセシビリティ法)を国内法制化し、民間企業にもアクセシビリティの義務を拡大しています。2025年6月から適用されるBFSG(アクセシビリティ強化法)では、電子商取引や銀行のオンラインサービスなどB2C向けサービスに高齢者・障がい者も利用可能な設計を義務付け、違反企業には罰金が科されます(注釈[4])。この法的枠組みにより、ドイツ企業はDX戦略にアクセシビリティを積極的に組み込むようになり、多くの企業が「アクセシビリティ対応は競争優位の戦略要素」と捉えています。こうした取り組みによって、コスト削減やブランド信頼性向上といった具体的なビジネス効果が生まれ、デジタル分野での競争力強化につながっています。
これらの事例から明らかなように、アクセシビリティとDXを統合することで企業は多大なビジネス効果を獲得できます。米国やEU諸国の事例からは、新たな市場開拓、ユーザー体験向上、ブランド価値強化など多面的な価値を生み出すことがわかり、シンガポールの事例は、包括的なデジタルサービスが高い行政効率と市民満足度をもたらすことを示しています。
一方で、アクセシビリティへの取り組みが十分とは言えない中国の状況を対比として見てみましょう。
中国では政府主導のDXが急速に進んでいる一方で、デジタル領域のアクセシビリティ対応には引き続き取り組むべき課題があると指摘されています。2021年には「YD/T 3329-2021 情報通信端末のアクセシビリティ設計技術要求」という新たな国家規格が発表されましたが、その適用範囲や実効性については議論の余地があるようです。特に、規格の遵守を監視する仕組みは限定的とされており、主に政府機関のWebサイトが対象となる一方で、民間企業における取り組みはまだ発展途上との見方もあります。
結果として、中国の8,500万人以上(人口の約6.2%)の障がい者がデジタル経済に十分参加できず、社会的・経済的損失を招いています。また、EUなど海外市場では2025年以降、アクセシブルでない製品・サービスは市場参入が制限される可能性があり、国際競争力の阻害要因ともなりかねません。
中国の例は私たちに重要な警鐘を鳴らしています。急速なDX推進にもかかわらずアクセシビリティへの対応が遅れれば、社会的排除を生むだけでなく、海外市場でのビジネスチャンス喪失や競争力低下という具体的なリスクにつながるのです。
日本のDX推進とアクセシビリティ対応における遅れと課題

世界の主要国がDXとアクセシビリティの統合を進める中、日本はどのような状況にあるのでしょうか。残念ながら、政策面と企業の取り組みの両面で課題が山積しており、早急な対応が求められています。
政策面の課題
日本政府は2021年にデジタル庁を新設し「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」を掲げていますが、長らく法的枠組みは弱く、民間企業には実質「努力義務」に留まっていました。2024年4月施行の改正障害者差別解消法により、民間事業者にも障がい者からの「合理的配慮」の提供が法的義務となりましたが、これは「求めに応じた個別対応」を義務化するもので、欧米のように事前にWebサイトをWCAG準拠にする義務までは課していません。
また、政策的優先順位においても課題があります。経済産業省が2018年に提唱した「2025年の崖」は、老朽化したレガシーシステムが2025年頃に一斉に更新時期を迎え、対応が遅れると最大で年間約12兆円の経済損失が生じる可能性を警告したものです。多くの企業がこの「崖」を乗り越えるためにシステム刷新を急ぎましたが、その際にアクセシビリティの視点は十分に考慮されず、主に内部業務効率化に焦点が当てられる結果となりました。こうした状況から、「利用者視点のDX」より「業務効率化のDX」が先行しがちだったのです。
企業の課題
日本企業の組織文化・経営姿勢も大きな要因です。海外ではDXをCEO自らが旗振り役となって企業戦略の柱として推進するのに対し、日本企業ではIT部門任せや一部現場改善に留まるケースが多いと指摘されています。世界的な経営コンサルティング会社である米McKinsey & Companyも「DXはCEOがリードし全社で推進すべきもの」と提言しています(注釈[5])が、日本では経営層のコミットメント不足がしばしばDX阻害要因となっています。
アクセシビリティについても同様で、「法的義務ではないから対応優先度が低い」「障がい者向けニッチ対応」という誤解から軽視されてきました。さらに人材・知識の不足も深刻です。アクセシビリティに精通したデザイナーやエンジニアは日本ではまだ少なく、教育機会も限られているため、企業内で対応しようにもノウハウがなく、不適切な対応や対応漏れが発生している実態があります。
特に問題なのは、日本が世界有数の高齢社会であるにもかかわらず、この認識が薄いことです。加齢に伴う視覚・聴覚の低下などアクセシビリティニーズは膨大で、対応の遅れは企業自ら顧客機会を逃していることを意味します。
世界の主要国の成功事例から日本企業が学ぶべき重要なポイントは、アクセシビリティを単なる社会的責任ではなく、競争力向上のための戦略的投資と位置づけることです。次のセクションでは、この視点に立ったアクションプランを提案します。
DX推進とアクセシビリティ統合のための5つのアクション

では、海外の成功事例に学び、日本企業が今すぐ実践すべき具体的な5つの方法を見ていきましょう。
1. 経営ビジョンへの組み込みと責任者配置
アクセシビリティ推進の第一歩は、企業トップのコミットメントです。英Barclays銀行(注釈[6])や米Apple社(注釈[7])のように、まず企業トップが「デジタル包摂」を経営理念に明示し、公にコミットします。ビジョンにもアクセシビリティ目標を盛り込み、社内外へ宣言することで、全社的な優先順位を示します。
併せて経営層のアクセシビリティ責任者を任命し、全社横断の推進体制を構築します。米Microsoft社では専門のChief Accessibility Officerを置き、全製品の包括的なアクセシビリティ向上を実現しています。この責任者には明確な権限とリソースを与え、進捗を定期的に経営会議で報告させることで、トップダウンの推進力を維持します。
2. 現状評価と目標設定(ギャップ分析)
アクセシビリティとDXの統合を成功させるためには、現状を正確に把握することが不可欠です。いきなり厳しい基準を目指すのではなく、まず自社のWebサイトやアプリ、社内システムのアクセシビリティ診断を実施し、現状の課題を可視化することから始めましょう。日本企業の場合、JIS X 8341-3(国際規格WCAG 2.1に準拠)のA基準達成を目指し、段階的にAA基準へと進むアプローチが現実的です。
英Legal & General社では、専門家による監査と障がい者ユーザーテストを通じて具体的な改善点を特定しました(注釈[8])。その結果、サイト公開直後に自然検索トラフィックが25%増(最終的に50%増)、コンバージョンが3ヶ月で2倍に跳ね上がるという劇的なビジネス効果が得られたと言います。この成功事例に学び、自社でも診断結果に基づき、「1年以内に主要ページをA基準準拠」「3年以内にAA基準達成」など、実現可能な目標と期限を設定し、社内のロードマップに落とし込むことで着実な進捗を図りましょう。
3. 開発プロセスへの統合(企画から実装まで)
アクセシビリティを後付けで対応すると、コストも時間も余計にかかります。DXプロジェクトのライフサイクル全体にアクセシビリティチェックを統合しましょう。具体的には、新規サービス企画時にアクセシビリティ要件を検討事項とし、デザイン段階でガイドラインチェックリストを適用、実装時にはアクセシビリティ検証ツールによるテストをスプリントに組み込みます。
先述したシンガポール政府のデジタルサービスチームは、開発プロセス全体にアクセシビリティチェックポイントを組み込み、障がい当事者を含むユーザーテストを推奨するガイドラインを確立しています。同様に、企業の開発プロセスにおいても、「企画・設計・開発・テスト」の一連のPDCAサイクルにアクセシビリティを組み込むことで、後から修正する手戻りを防ぎコスト増を回避できます。
4. 社員教育と専門人材の育成
英Barclays銀行では社員向けトレーニングとガイドライン整備により、アクセシビリティ意識を企業文化として浸透させ、全従業員が自分事として取り組む体制を築きました(注釈[9])。日本企業でも同様に、社員へのアクセシビリティリテラシー向上施策を速やかに開始すべきです。
まずはUXデザイナー、エンジニア、マーケターなど関係者に基本研修を実施し、スクリーンリーダー操作体験や事例紹介を通じて理解を深めましょう。重要なのは「自分たちの業務がどのようにユーザーの体験に影響するか」を腹落ちさせることです。
5. インクルーシブな調達とパートナーシップ
アクセシビリティ推進は自社だけでは完結しません。英国政府のデジタルサービス部門は、すべてのIT調達においてアクセシビリティ要件を標準化し、サプライチェーン全体でのアクセシビリティ向上を実現しています。日本企業も同様に、発注するシステム開発や購入するソフトウェアについてアクセシビリティ準拠を契約条件に含めることで、バリューチェーン全体での取り組みを促進できます。
また、欧米企業は障がい者団体との戦略的パートナーシップを積極的に構築しています。米Microsoft社は障がい者コミュニティと連携し、製品開発サイクルの早い段階からフィードバックを取り入れる”Inclusive Design”アプローチを採用しています(注釈[10])。日本企業も障がい者団体や研究機関との協力関係を築き、ユーザーテストやアイデア創出を行うオープンイノベーションを推進することで、より質の高いアクセシビリティ対応が可能になります。
これら5つのアクションは互いに連携し合い、企業全体のアクセシビリティ成熟度を高めていきます。海外の成功企業が示すように、アクセシビリティへの取り組みは、顧客体験の向上、市場拡大、ブランド価値向上など、ビジネス成長のエンジンとなります。成功事例を社内で共有し、モチベーションを維持することで、長期的な取り組みを支えていきましょう。
DX推進とアクセシビリティの統合がもたらすビジネス効果
DXとアクセシビリティの統合は、新たなビジネス価値を創出する強力な原動力となります。企業がシステムやプロセスの刷新に留まらない真のデジタル変革を目指すなら、アクセシビリティの視点は不可欠です。なぜなら、アクセシブルなデジタルサービスは幅広いユーザー層へのリーチを可能にし、DXの本質である「顧客体験の向上」と「新たな価値創造」を最大化するからです。
また、アクセシブルなDXは企業の持続可能性も高めます。世界13億人以上の障がい者市場にアクセスできるだけでなく、高齢化が進む日本社会において、ユーザビリティに優れたサービスは顧客基盤の維持・拡大に直結します。DX推進の過程でアクセシビリティを組み込むことで、社内システムの使いやすさも向上し、従業員の生産性向上や多様な人材の活躍も促進されます。法規制の強化、高齢化の進展、グローバル競争激化の中で、日本企業はDXとアクセシビリティの統合戦略をビジネス競争力の源泉として積極的に推進していくべきでしょう。
リンク集
注釈[1] アクセシビリティ教育推進団体「Teach Access」:teachaccess.org
注釈[2] シンガポール政府のデジタルサービス基準(DSS)強化策:tech.gov.sg
注釈[3] デンマークの統合デジタル戦略2022-2025:en.digst.dk
注釈[4] ドイツのBFSG(アクセシビリティ強化法):gesetze-im-internet.de/bfsg/
注釈[5] 米McKinsey & Companyのデジタル変革に関する提言:mckinsey.com
注釈[6] 英Barclays銀行のアクセシビリティへの取り組み:home.barclays/accessibility/
注釈[7] 米Apple社のアクセシビリティへの取り組み:apple.com/accessibility/
注釈[8] 英Legal & General社のアクセシビリティ改善事例:dusted.com
注釈[9] 英Barclays銀行のアクセシビリティ文化構築事例:w3.org
注釈[10] 米Microsoft社のインクルーシブデザインアプローチ:inclusive.microsoft.design/