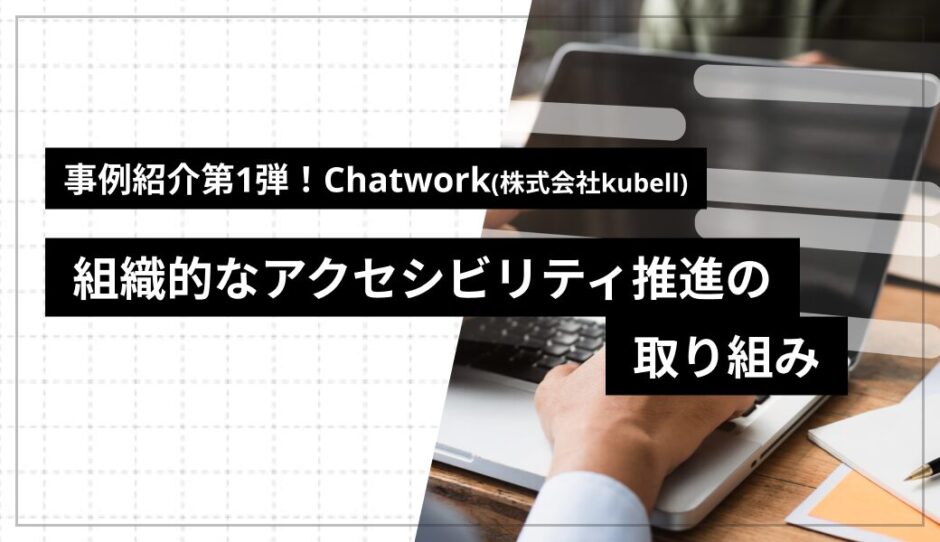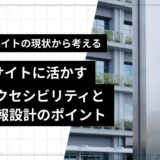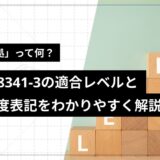Webアクセシビリティへの社会的関心が高まる以前の2017年、ビジネスチャットツール「Chatwork」を提供するChatwork株式会社(現株式会社kubell)は、組織全体でアクセシビリティを推進する包括的な取り組みをスタートさせました。
本記事では、早くから先進的な取り組みを行ってきた同社の事例から、組織としてアクセシビリティ対応を推進するためのヒントをご紹介します。方針策定から社内啓蒙、そしてユーザーフィードバックを活かした継続的な改善まで、実践に役立つ具体的な取り組みをご覧ください。
アクセシビリティ方針策定:事業戦略としての位置づけ
ビジネスチャットツール「Chatwork」は、日々の業務コミュニケーションを支えるサービスです。Chatwork株式会社がアクセシビリティを「使いやすさの向上」だけでなく「働く権利の保障」として捉えた背景には、サービス特性への深い理解がありました。
「なぜ」「誰に」「何のために」「どのように」を洗い出し整理しながら、最初に取り組んだのはスローガンの創出でした。細かな定義も必要ですが、1本芯の通ったスローガンを立てることで、すべての答えを導き出しやすくなります。方法としては、Chatworkのミッションのキーワード「働く」というワードを軸に、アクセシビリティではどう貢献できるのか、すべきか、を考えていくルートです。Chatworkが使えない=働けない状態にしてはいけない、ということをメッセージに含んでいます。
最終的に、「働くことは誰もがもっている権利です」という言葉を決め、Chatworkが提供すべきサービスの状態を明文化しました。
私たちのアクセシビリティ方針のポイントは、明確に「社内外で啓蒙していくためのものであると同時に、実践へつなげるためのもの」と定義しているところです。社外への発信のみに留まるのではなく、社内への啓蒙のツールとしても活用していくことを前提に設計しました。
出典:「働く」を「権利」と定義したChatworkアクセシビリティ方針決定の裏側
2017年4月、Chatwork株式会社は組織としての明確な方針を策定しました。特筆すべきは、アクセシビリティへの取り組みを単なるCSR活動ではなく、ビジネスインフラとしての信頼性を確保するための重要な事業戦略として位置づけた点です。
現在、株式会社kubellの「アクセシビリティ方針と試験結果」のページでは、目標としてJIS X 8341-3:2016【レベルAA】準拠を掲げ、対応度試験の結果も公開しています。この透明性の確保は、ユーザーに対する誠実さを示すと同時に、自社のアクセシビリティ対応状況を客観的に把握し、継続的な改善につなげる役割も果たしています。
方針策定においては、単なる対外的宣言ではなく社内啓蒙にも活用することを前提としたことで、利用者層の拡大と信頼性向上という事業価値を生み出しつつ、組織全体での理解促進へもつなげていったのです。
社内の理解を醸成する:小さな一歩からの意識改革

アクセシビリティに対する意識を組織全体に浸透させるには、まず理解を深める土壌づくりが欠かせません。Chatwork株式会社のアクセシビリティ推進担当者である守谷氏の経験によれば、周囲に関心を持つ人が少ない状況でも始められる効果的な方法があるといいます。
身近なテーマの共有からはじめる
アクセシビリティを社内に根付かせるには、まず関心を持つきっかけを提供することに注力すると効果的です。Chatwork株式会社では、まず自分にとって身近なテーマをもとに、小規模な共有を行うことからはじめました。表面的な知識では、重要性や本質的な価値を伝えることは困難です。わかりやすく説明できる自分の関心や学びを伝えることで、周囲の興味を引き出し、次の変化をもたらしたといいます。
この取り組みからは、アクセシビリティ推進において「まずは関心を持ってもらう」ことと「理解を深めるきっかけを作る」ことの両方が重要だと学べます。自社での実践を考える際は、各メンバーの業務や得意分野に近いトピックから共有していくことで、より自然な形で関心を広げ、理解を促すことができるでしょう。
相互理解を育む場をつくる
アクセシビリティの理解には、知識の習得だけでなく実践的な学びの場が重要です。Chatwork株式会社では、ガイドラインの勉強会において、参加者それぞれが担当項目を深く掘り下げて共有し合う形式を採用するなど、相互学習の機会を重視してきました。さらに、スクリーンリーダーの体験会など、実際の利用シーンに触れる機会を設けることで、アクセシビリティをより身近な課題として認識できる工夫も行ったといいます。
実践を通じた相互学習の場を設けることで、アクセシビリティは特定の専門家だけの課題ではなく、組織全体で取り組むべきテーマとして認識されていきます。自社で実践する場合も、メンバーが主体的に参加できる機会を作ると、より深い理解と実践につながるでしょう。
お互いに学び合い、実践を重ねることで、アクセシビリティへの理解はより確かなものとなります。この段階で培われた組織の理解と共感が、次のステップである持続的な改善活動の基盤となるのです。
参考資料:「アクセシビリティの啓蒙Tipsちょっと見せ」
守谷絵美氏(Chatwork株式会社)講演/GAAD Japan 2023
継続的な改善を支える:日常業務に根付く仕組みづくり
理解の土壌ができてきたら、次は持続可能な改善の仕組みづくりが重要です。アクセシビリティへの関心を一時的なものではなく、組織文化として定着させることが求められます。
日々の業務に溶け込ませる情報共有
アクセシビリティに関する情報や知見を共有する際は、セミナーなどのイベントよりも、日常的な接点を増やすことが効果的です。特定のタイミングだけでなく、普段の業務の中で自然と目にする機会を作ることで、持続的な意識の向上が期待できます。
情報共有の場を設計する際は、目的に応じて使い分けることが有効です。Chatwork株式会社では、ニュースやトレンド情報を共有する場と、具体的な実装や対応について相談する場を分けて、チャットチャンネルを運用しているといいます。情報の性質に応じて共有の場を整理することで、参加者にとって関心のある情報にアクセスしやすくなり、自然な形での知見の蓄積と活用が促進されます。
日常的な情報共有の場を設けることは、大がかりな施策を必要とせず、どの企業でも始められる効果的なアプローチと言えるでしょう。情報に触れる頻度を増やすことで、メンバーの関心を徐々に高め、自発的な行動を促すきっかけともなり、アクセシビリティへの意識を組織に根付かせることができます。
それぞれの立場に応じた伝え方の工夫
アクセシビリティの社内浸透において、Chatwork株式会社が特に重視しているのは「誰に対してどう伝えるか」という点です。技術的な側面だけでなく、それぞれの立場や関心に合わせた説明を心がけることで、理解と実践が進みやすくなります。
社内でWebアクセシビリティ対応を進めるための共有(勧誘)方法が、対象者によってそれぞれ変わります。
- 聞いたこともない人には、Webアクセシビリティ対応をすると何がいいのか、しないとどういう懸念があるのかを明確に
- 実装者には、具体的な対応方法を学ぶ/考える機会を増やす
- 情報を加工する力を持った人には、今後の展望を含めた情報設計/提供の重要性を伝える
それぞれに響く形で伝えられると、割とすんなり受け入れてもらえるという印象です。
出典:社内で「Webアクセシビリティ」を伝えるためにやったこと
このように、理解促進のための土壌づくりから、日常的な情報共有、そして個々の役割に応じたアプローチまで、段階的に仕組みを整えていくことで、アクセシビリティへの取り組みは組織に根付いていきます。特別なプロジェクトではなく、通常の業務プロセスの一部として定着させることが、持続的な改善を実現する鍵となるのです。
ユーザーの声を活かす:フィードバックを成長の機会へ

アクセシビリティの改善において、ユーザーからのフィードバックは貴重な気づきをもたらします。Chatwork株式会社では、ユーザーの声を活かした改善と、当事者視点の理解を深めるための取り組みを行ってきました。
実際のユーザーの声からの学び
アクセシビリティ対応を進める上では、技術的な対応だけでなく、社内に根付いた取り組みが大きな支えになります。例えば、Chatwork株式会社にスクリーンリーダー利用者から「アカウント登録時の画面がスクリーンリーダーだと操作困難である」という問合せが寄せられた際には、社内に蓄積された知見や既存の仕組みが迅速な対応を可能にしたといいます。
この経験を通じて、同社では新たな課題の解決にも取り組みました。特定の有識者による取り組みだけでなく、組織的な対応体制の必要性を認識し、課題の見える化や実装時のチェックリスト整備、アクセシブルなUIコンポーネント配布といった基盤整備に着手しています。これらの取り組みは、個々の知識や関心に左右されずに、一定の品質を確保するための仕組みづくりとして有効です。
このように、実際のユーザーからの声を「一時的な対応」で終わらせるのではなく、「成長の機会」として活かすことで、組織全体のアクセシビリティへの取り組みがより成熟していきます。
参考資料:「ユーザーの問い合わせがアクセシビリティ改善を推進した話」
釜堀友基氏(Chatwork株式会社)講演/GAAD Japan 2024
インクルーシブな企業訪問からの学び
ユーザーからの問い合わせだけでなく、積極的に利用現場に出向いて声を聞くことからも学びが得られます。Chatwork株式会社は、障がいのある方々の雇用促進に先進的に取り組む株式会社カムラックを訪問し、実際の利用環境やニーズを直接観察する機会を作りました。
Chatworkで言うところのアクセシビリティは、サービスやツール(アプリ)への対応にフォーカスすることが多く、自然と対応(作業)範囲も狭まっていきます。今回カムラックの働き方を伺うまでは、私の意識でも自然と視野が狭まり、姿勢も狭くなっていたように思います。
Chatworkはツールやサービスを提供するだけの会社ではなく、「働き方」を提案する企業です。色々なケースの障害者、あるいは障害がなくても労働弱者にならざるをえない場合も多々あります。そういった場面で、すべてのスタッフを活かせる組織にするヒントを今回たくさん見られた気がします。
出典:インクルーシブな企業「株式会社カムラック」を訪問してきました
この訪問記から、アクセシビリティ対応を考える際には「特定の機能やUIの改善」にとどまらず、「ユーザーが直面するより広い課題」に目を向けることが重要だということが伝わってきます。ユーザーの声を聞く際も、直接的な機能の要望に応えるだけでなく、背景にある利用環境や業務上の課題を読み取ることが、実践的なフィードバックの活用につながります。
こうした視点は、あらゆる企業のアクセシビリティ対応に活かすことができます。自社の対応が「特定のユーザー向けの機能追加」にとどまっていないかを見直し、より多くの人にとって使いやすい形を考えることで、新たな課題や改善の余地が見えてくるでしょう。ユーザーの声を「単なるリクエスト」として扱うのではなく、背景にあるニーズを深掘りすることで、より実践的で意義のある改善が実現できるようになります。
持続可能なアクセシビリティ推進に向けて
Chatwork株式会社の事例から学べる重要なポイントは、アクセシビリティを一時的な対応ではなく、組織文化として定着させる姿勢です。自社の理念に基づいた明確な方針のもと、効果的な啓蒙活動を地道に展開し、ユーザーの声を活かした改善を進めることで、持続可能な取り組みが実現します。
アクセシビリティの組織的な推進に取り組むなら、まずは自社のサービスや製品が果たすべき社会的役割を見つめ直すことから始めるとよいでしょう。技術的な対応以前に、なぜアクセシビリティに取り組むのかという本質的な問いに向き合うことで、一過性のプロジェクトではなく、継続的な取り組みの基盤が築けます。