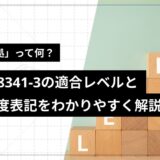近年、WEBアクセシビリティ(Web Accessibility)に関する訴訟が急増し、企業にとって重要なリスク管理の一環となっています。特にアメリカでは、ADA(Americans with Disabilities Act:障害を持つアメリカ人法)に基づき、障害者が利用できないウェブサイトやアプリに対する訴訟が相次いでいます。本記事では、代表的な訴訟事例とその影響について詳しく解説し、最近のアクセシビリティ訴訟の傾向についても触れます。
代表的なWEBアクセシビリティ訴訟事例
1. Domino’s Pizza訴訟(Robles v. Domino’s, 2016-2022)

視覚障がい者のGuillermo Robles氏は、Domino’s Pizzaのウェブサイトやモバイルアプリが、スクリーンリーダーを使用して操作できず、ピザの注文ができなかったことから訴訟を起こしました。Robles氏は、ADA(障害を持つアメリカ人法)に基づき、Domino’sのウェブサイトとアプリも店舗と同様に誰でもアクセスできるようにする義務があると主張しました。
原告側の請求額:
カリフォルニア州のUnruh法に基づき、アクセス不能だった各回について最低$4,000の賠償請求。
判決または和解額:
2019年の第9巡回控訴裁判決でADA違反が認められ、2021年6月に地裁が$4,000の賠償金とWCAG 2.0準拠を求める差止命令を発令。その後、2022年に和解が成立したが、詳細な条件は非公開となっている。
最終的な結果:
控訴・最高裁上訴を含めた長期の法廷闘争により、高額な弁護士費用が発生したと推測されている。訴訟の結果、Domino’sは最終的にアクセシビリティ対応を進める形となった。
参照:boia.org
2. Winn-Dixie訴訟(Gil v. Winn-Dixie, 2016-2021)

視覚障がい者のJuan Carlos Gil氏は、スーパーマーケットチェーンWinn-Dixieのウェブサイトで、処方薬のリフィルやデジタルクーポンが利用できないとして提訴。Gil氏は、Winn-Dixieのウェブサイトが障がい者にとっても利用可能であるべきだと主張しました。
原告側の請求額:
金銭的賠償は求めず、サイト改善命令と弁護士費用の補填を要求。
参照:littler.com
判決または和解額:
2017年:地裁判決 → Winn-DixieにWCAG 2.0 AA準拠を求める3年間の差止命令。
2021年:控訴審 → ウェブサイトはADAの「公共の場所」に該当しないと判断され、Winn-Dixieが逆転勝訴。
訴訟費用:
原告弁護士費用$99,879の支払いが一時命じられたが、控訴により無効化。Winn-Dixie側は4年以上の訴訟対応で高額な弁護士費用を負担したと推測される。
3. Harvard/MIT訴訟(NAD v. Harvard/MIT, 2015-2020)

全米ろう者協会(NAD)は、Harvard大学とMITが提供するオンライン講義動画に字幕がないことが聴覚障害者に対する差別に当たるとして提訴。NADは、ADAおよびリハビリテーション法に基づき、すべての動画に正確な字幕を付与するよう求めました。
判決:
2019-2020年に和解成立。
すべての公開オンラインコンテンツに高品質の字幕を付与することを義務化。
大学側も5年間の法務対応により大規模の弁護士費用を支払ったと推測されている。
4. Scribd訴訟(NFB v. Scribd, 2015)

電子書籍プラットフォーム「Scribd」が視覚障害者向けのスクリーンリーダーに対応していなかったため、全米盲人連盟(NFB)が提訴。
スクリーンリーダー対応の差止命令と訴訟費用の補填を要求。
2015年に和解成立。
Scribdは2017年までにウェブサイトとアプリをスクリーンリーダー対応に改修することを約束。
金銭的な和解金はなし。
近年の訴訟における社会的・業界的なインパクト

WEBアクセシビリティ訴訟の増加は、企業だけでなく業界全体にも大きな影響を及ぼしています。特に、企業のコンプライアンス意識の向上やUX(ユーザーエクスペリエンス)の向上、さらには法制度の変化にまで波及しており、業界全体での取り組みが求められています。
WEBアクセシビリティに関する意識の高まり
10年前にはほとんど知られていなかったWCAG(Web Content Accessibility Guidelines)が、今や「ADAコンプライアンス」=「WCAG遵守」と認識されるほど普及しています。業界カンファレンスや資格(IAAPのCPACCなど)を通じて、アクセシビリティに関する専門知識を学ぶ機会が増えています。
業界全体のUX全体の向上
アクセシビリティの向上は、障害者だけでなく一般ユーザーにも恩恵をもたらしました。たとえば、
・字幕は騒がしい環境でも有用。
・ALTテキストはSEOの向上に貢献。
・キーボード操作や音声操作対応は、モバイルユーザーや高齢者にも利便性を提供。
結果として、サイトの使い勝手が改善され、ブランドイメージの向上にも繋がっています。
乱訴問題
一方で、同じ原告が大量に訴訟を起こす“drive-by”訴訟に対する批判もあります。企業側からは「弁護士費用目的では?」との声もあり、一部のケースでは誠実な訴訟というよりも訴訟ビジネスの側面が指摘されています。しかし、現行法では明確な歯止めがないため、未整備のウェブサイトは依然として訴訟リスクが高い状況にあります。
最近の動向と今後の展望

WEBアクセシビリティの重要性が増す中で、新たな技術や法制度の動向にも注目が集まっています。従来のウェブサイトだけでなく、モバイルアプリやマルチメディアコンテンツに対するアクセシビリティ要件が強化されつつあり、企業の対応が急務となっています。また、AI技術の進化とともに、自動キャプションやアクセシビリティ補助ツールの品質向上も期待されています。一方で、規制や法改正の動きも活発化しており、今後の訴訟リスクを低減するためには、各国の最新動向を注視しながら適切な対応を進めることが求められます。
新領域の争点
モバイルアプリ、動画、ポッドキャスト
ウェブサイトだけでなく、モバイルアプリのアクセシビリティや動画への字幕・音声解説、ポッドキャストの文字起こしが訴訟の対象として広がっています。特に、教育機関や企業研修の動画コンテンツは訴訟リスクが高く、早急な対応が求められています。
AIの活用
AIを用いた自動生成の代替テキストや字幕の品質が問われるようになっています。特に、自動キャプションの誤認識率や、AIチャットボットのUIがスクリーンリーダーで使えないといった問題が新たな争点として浮上しています。
アクセシビリティ・オーバーレイへの議論
JavaScriptのプラグインを挿入するだけでアクセシビリティを向上させる「オーバーレイ」技術が注目されていますが、根本的なコード修正を行わないため、逆に問題を増やすケースも報告されています。訴訟対策としては十分ではなく、慎重な対応が求められます。
規制と立法の動き

DOJによる新ルール
2023年には、ADA Title II(州・地方自治体向け)に関するウェブアクセシビリティ規則案が提出されました。今後、Title III(民間企業)にも同様の規制が導入されれば、WCAG準拠が法令化される可能性があります。
EUの2025年施行
欧州ではEuropean Accessibility Act (EAA) により、主要な民間事業にもWCAG水準の遵守が義務付けられます。欧州市場に展開する企業は、今後の規制強化を視野に入れた対策が必要です。
グローバル化と標準化
各国がWCAG基準を法や指令に取り入れる動きが加速しており、企業は「アクセシビリティ・バイ・デザイン」の考え方を採用し、最初からアクセシブルな設計を取り入れることが求められています。
WEBアクセシビリティは単なる訴訟対策ではなく、企業の社会的責任として取り組むべき重要な課題となっています。
誰もがウェブの恩恵を受けられる社会づくり
ウェブは企業のビジネス基盤であり、アクセシビリティは「特別な対策」ではなく、ユーザーにとっての基本的な使いやすさの確保に近づいています。今後は、ADA訴訟による外部圧力というより、法令の明文化や社会通念として「ウェブは当然誰にでも使えるもの」という認識が定着すると期待されます。現時点では、米国を中心に訴訟リスクが依然として高いため、企業は予防的にウェブアクセシビリティ対策を進め、持続的な改善プロセスを構築することが重要です。