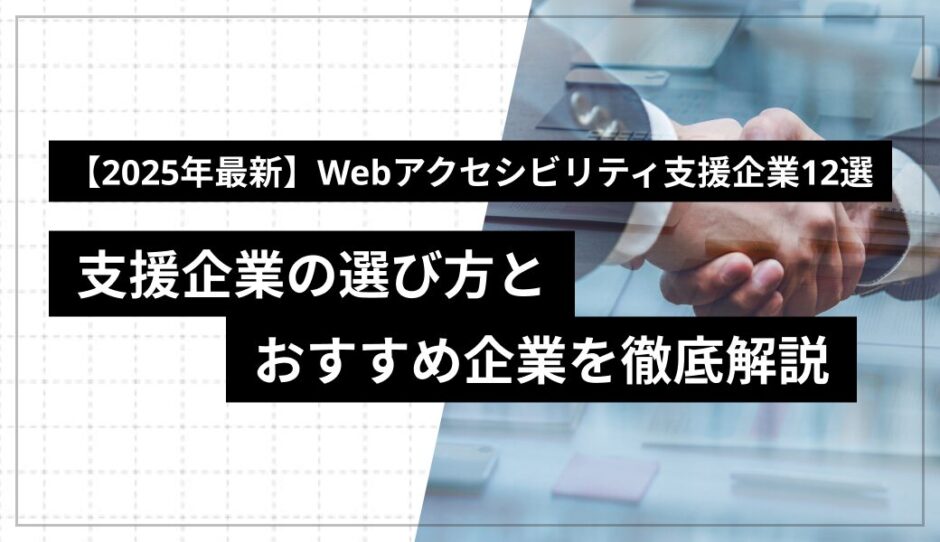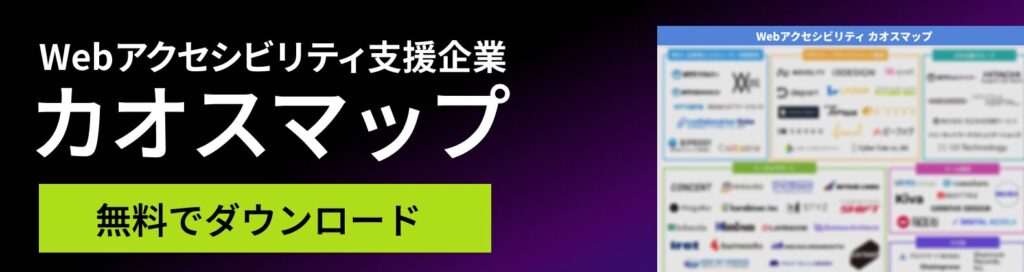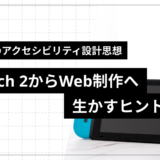Webアクセシビリティ対応の重要性が高まる中で、「どの企業に何を相談すればいいのか」と悩んでいる担当者の方も多いのではないでしょうか。支援企業は数多く存在しますが、それぞれ得意分野や支援スタイルが大きく異なるため、自社に最適なパートナーを選ぶことが成功の鍵となります。
本記事では、支援企業を選ぶ前に知っておきたいポイントから、3つの主要な支援タイプの特徴、そして各タイプのおすすめ企業12選まで、役立つ情報を網羅してお届けします。記事を最後まで読めば、自社に合う支援企業への相談に向けて具体的なアクションを起こせるようになるでしょう。
支援企業を探す前に知っておきたい4つのポイント
アクセシビリティ支援企業への相談をより有意義なものにするため、押さえておくとよい基本的なポイントは下記の4つです。
- 対象サイトの規模感
- 目指すアクセシビリティ適合レベル
- 対応範囲の選択肢
- 予算の目安
これらの基本知識があると、支援企業から具体的な提案を受けやすくなります。まだ決まっていない項目があっても問題ありませんので、参考情報として確認していきましょう。
対象サイトの規模感
対象となるWebサイトの規模は、支援内容や費用に大きく影響します。一般的には以下のように分類できます。
小規模サイト(〜10ページ) コーポレートサイトやランディングページなど、比較的シンプルな構成のサイトです。ページ数が少ないため短期間での対応が可能で、費用も比較的抑えやすい規模感と言えるでしょう。
中規模サイト(10〜30ページ) 企業の本格的なWebサイトやサービスサイトなど、複数のコンテンツカテゴリを持つサイトです。この規模になると体系的なアプローチが必要になってきます。
大規模サイト(30ページ〜) ECサイトや大企業のコーポレートサイトなど、多数のページと複雑な機能を持つサイトです。段階的な対応やプロジェクト管理の重要度が高くなります。
さらに大規模なサイトの場合 動的に生成される同一構成のページ(記事ページや商品ページなど)が多数あるサイトでは、サンプリング調査が有効です。JIS X 8341-3:2016試験実施ガイドラインでは、合否判定に十分なページ数の目安として40~50ページ程度と示されています。サンプル数は全体の総ページ数に比例して決まるものではないため、規模の大きなサイトでも必要以上に試験対象のページ数を増やす必要はありません。
目指すアクセシビリティ適合レベル
アクセシビリティには、国際的なWCAGガイドラインや日本のJIS規格によって定められた明確な基準があります。どのレベルを目指すかは支援企業と相談しながら決めていけば大丈夫ですが、基本的な違いを理解しておくとよいでしょう。
A準拠 or AA準拠
- A準拠:基本的なアクセシビリティ要件を満たすレベル
- AA準拠:より幅広い要件を含む、多くの企業や組織で目標とすることを推奨されるレベル
重要なのは、AA準拠を宣言するには、Aレベルのすべての達成基準を満たした上で、さらにAAレベルの達成基準もすべて満たすことが、基本的には必要であるという点です。つまり、上位レベルを目指すほど、試験対象となる項目が増え、検査や改修が必要な範囲も広がるということを理解しておきましょう。最終的には、企業としてどこまで重視するか次第ですので、大企業でもA準拠までの対応としている場合や、ページ数が比較的少ない中小企業でもAA準拠を実現している場合もあります。
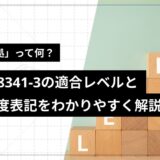 「AA準拠」って何?JIS X 8341-3の適合レベルと対応度表記をわかりやすく解説!
「AA準拠」って何?JIS X 8341-3の適合レベルと対応度表記をわかりやすく解説!
JIS X 8341-3 or WCAG 2.2
- JIS X 8341-3:日本の実情に即したWebアクセシビリティ基準
- WCAG 2.2:国際的なWebアクセシビリティガイドライン
JIS X 8341-3は、日本語の特性や国内の利用環境に配慮したアクセシビリティ基準を提供しているため、日本では多くの企業や組織がJIS X 8341-3に沿ってWebアクセシビリティ対応を進めています。ただし2025年6月現在、JIS X 8341-3はWCAG 2.0準拠の状態であり、WCAG 2.1や2.2への対応がまだ行われていません。よって、グローバルに事業を展開する企業は、より新しいWCAGの要件も考慮に入れる必要があります。
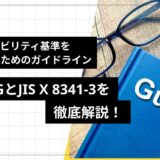 アクセシビリティ基準を理解するためのガイドライン – WCAGとJIS X 8341-3を徹底解説!
アクセシビリティ基準を理解するためのガイドライン – WCAGとJIS X 8341-3を徹底解説!
最終的には、適合しているかどうか以上に、サイトへ訪問する障がい当事者の方がどう感じるかを重視することをおすすめします。規格準拠と実際の使いやすさの両方を考慮した目標設定について、支援企業と相談しながら決めていくことが重要です。
対応範囲の選択肢
アクセシビリティ支援サービスには、診断のみを行うものから改修を含むものまで、対応範囲が異なる複数のメニューがあります。どのようなサービス内容があるかを知っておくと、自社の状況に応じた相談ができるようになります。
簡易診断 サイト全体の概要を把握し、主要な課題を洗い出すための初期調査です。現状把握の第一歩として、比較的短期間・低コストで実施できるため、多くの企業がここからスタートしています。
詳細診断 より詳細な検査を行い、具体的な改修箇所と対応方法を明確にします。本格的な改修に取り組む前の段階で実施されることが多く、改修計画の策定に欠かせないプロセスです。
全体改修 診断結果をもとに、実際にサイトの改修を行います。デザインの調整からコーディング、場合によってはサイト構造の見直しまで、包括的な対応が必要となります。
多くの企業では、まず簡易診断で現状を把握し、その結果を踏まえて詳細診断や改修の検討を進めるケースが一般的です。
予算の目安
アクセシビリティ対応の費用は、サイト規模・目指す適合レベル・対応範囲によって変動します。支援企業と相談する際の参考として、一般的な目安をご紹介します。
簡易診断(10~50万円) 現状把握と優先課題の特定が主な目的です。サイト規模が小~中規模であれば、この範囲で実施できることが多いです。
詳細診断(100~300万円) 本格的な問題発見と改善計画の策定を行います。対象ページ数や検査項目の多さによって費用が変動します。
全体改修・運用体制構築(300万円~) 抜本的な改善と継続的な体制構築を目指す場合の費用感です。サイト規模や改修範囲によっては、より大きな予算が必要になることもあります。
ただし、これらはあくまで目安であり、サイトの技術的要件や複雑さ、求める品質レベルによって費用は大きく変動することを理解しておきましょう。
多くの支援企業が無料相談を実施しているので、まずは相談してみることをおすすめします。「どこまで対応したいか」「どんな状態を目指すべきか」といった内容は、決まっていないことの方が多いでしょう。また、対象サイトの現状や課題も、専門的な視点からの診断を受けてみないとわからない部分が多いものです。相談を通じて、必要な対応レベルや現実的な費用が見えてきますので、細かいところまで明確になっていなくても心配はありません。
自社に合う支援企業の見つけ方 – 3つの支援タイプの紹介

アクセシビリティ支援企業は、それぞれ得意とする領域や支援スタイルが異なり、大きく3つのタイプに分けることができます。それぞれの特徴を理解し、自社に最適なタイプの企業への相談を検討してみてください。
障がい当事者によるユーザー体験重視型
実際に障がいのある方によるユーザーテストを実施し、規格への適合以上に「本当に使いやすいか」を検証して支援を行う系統の企業です。様々な障がい特性を理解した専門家が、具体的で効果的な改善提案を行います。
アクセシビリティの本質は「すべての人が使いやすいWebサイト」の実現にあります。このタイプは、技術的な基準をクリアするだけでなく、リアルなユーザー体験に焦点を当てることで、真の意味でのアクセシビリティ向上を目指せるのが大きな特徴です。
規格への適合も考慮しながら、何より障がい当事者の方々の実際の声を重視したい企業、顧客体験や使いやすさを最優先に考えたい企業に適しています。
デザイン・ブランドイメージ重視型
Webデザインや制作の豊富な経験を活かし、優れたデザイン性を保ちながらアクセシビリティ要件を満たす系統の支援企業です。色彩設計、レイアウト、タイポグラフィなどのデザイン要素を調整しながらアクセシビリティを実現する技術に長けており、企業のブランド価値を損なわない改善提案を行います。
自社にデザイナーやデザインチームがいない企業、ブランドコンセプトとアクセシビリティの両立を重視したい企業に向いています。
体制重視・トータルサポート型
規格への確実な準拠からガイドライン策定、品質管理プロセスの導入まで、総合的な支援を提供する系統の企業です。単発の改修にとどまらず、研修や社内体制の構築など、企業のニーズに応じて長期的な視点でサポートします。
組織として本格的にアクセシビリティに取り組みたい企業、継続的な運用体制まで構築したい企業に適しています。
それでは次に、支援タイプごとに代表的な企業をご紹介します。自社に不足している点や重視したい観点をふまえて、最も適したタイプの企業を選ぶとよいでしょう。
障がい当事者によるユーザー体験重視型
このタイプの企業は、実際の障がい当事者の方々の視点を重視し、規格への適合だけでなく「本当に使いやすいサイト」の実現を目指します。アクセシビリティの本質である「実際の使いやすさ」を大切にしている点で、多くの企業にとって有効なアプローチと言えるでしょう。ユーザーの声を直接聞けることで、社内の意識改革にもつながりやすいのが特徴です。
WANT MORE株式会社

WANT MORE株式会社は2020年に設立された比較的新しいアクセシビリティ専門企業です。VALT JAPAN株式会社(15,000以上の障がい者就労支援施設と連携するBPOプラットフォーム)との提携により、様々な障がい当事者にサイトの操作評価を依頼し、実際の使いやすさを検証するサービスを展開しています。
同社は障がい者にとって使いやすいWebサイトを実現すると同時に、一般的なユーザー体験(UX)を損なわない、バランスの取れた改善を重視しています 。手軽に現状を把握したい企業向けに提供している「ライト診断サービス」では、実際に障がいのある方による評価を通じて効率的に課題を発見できるため、本格的な診断に踏み切る前の準備段階として、あるいは限られた予算内で効果的な改善点を見つけたい場合に有効です。
また、アクセシビリティに関する専門メディア「Webアクセシビリティ・リサーチラボ」の運営を通じて、アクセシビリティの基本から最新動向まで幅広い情報を発信しています。さらに、ユーザーテストの結果をもとに「アクセシビリティ検査証明書」を発行するサービスも提供しており、「実際に障がいのある方がチェック済み」という実効性の高い対応を実現できます。
WANT MORE株式会社のWebアクセシビリティ支援サービスはこちら
NTTクラルティ株式会社

NTTクラルティ株式会社は、実際に障がいのある社員が音声ブラウザなどの支援技術を駆使し、当事者の視点から診断を行う点が最大の強みです。機械的なチェックツールだけでは発見が難しい、サイトの構造的な問題点を的確に捉え、当事者だからこその気づきを重視した実効性の高いアクセシビリティ改善を提供します。
診断結果はWebサイトのスクリーンショットを多用した視覚的に分かりやすいレポート形式で報告され、専門知識がない担当者でも直感的に理解できるよう配慮されています。JIS規格への準拠が確認されたWebサイトには独自の「準拠マーク」(登録商標)を掲載できるため、企業のアクセシビリティへの積極的な取り組みを対外的に示すのにも有効です。
BIPROGYチャレンジド株式会社

BIPROGYチャレンジド株式会社(ビプロジーチャレンジド)は、障がい者の雇用促進を目的として設立された特例子会社であり、従業員の多くが何らかの障がいを有しています。この企業構造そのものが、同社のWebアクセシビリティ検査サービスにおいて、当事者の視点を深く、かつ組織的に組み込むための基盤となっています。
また、豊富な開発実績を持つBIPROGYグループの技術者が品質管理を担当しているため、診断結果に基づく改善提案においても、効果的なサポートが期待できるでしょう。
特定非営利活動法人Collable
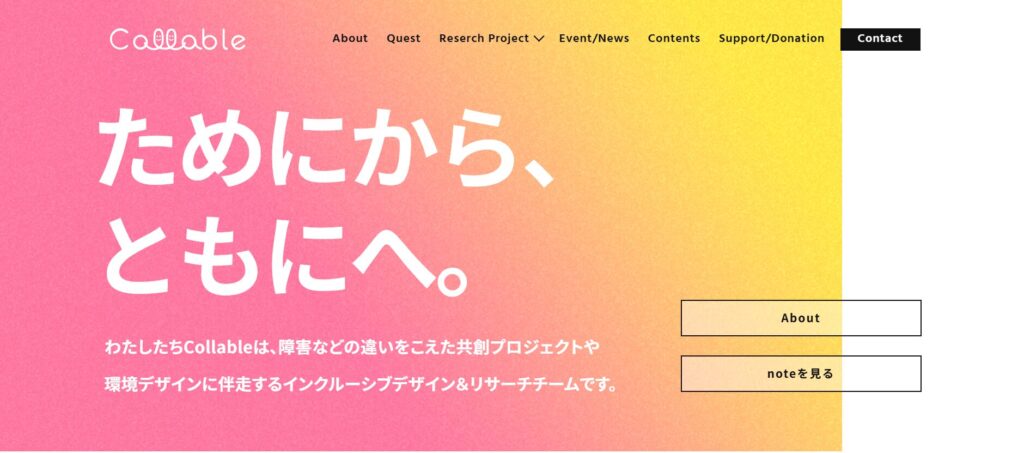
特定非営利活動法人Collable(コラブル)は、10年以上のインクルーシブデザイン経験を基盤に、視覚障がい(全盲、ロービジョン)から視覚過敏性のある発達障害まで、多様な特性を持つ当事者チェッカーによる診断を実施している点が特徴です。単にユーザーの声を聞くだけでなく、潜在的なニーズを洞察して、真にインクルーシブなデザインの実現を目指しています。
コスト面では、「1ページ30,000円(税別)から」という、比較的手頃な価格で診断サービスを開始できるプランを提供しています。特に予算が限られている中小企業やNPOにとって、アクセシビリティ向上の第一歩を踏み出しやすくする料金設定です。
デザイン・ブランドイメージ重視型
このタイプの企業は、Webデザインや制作の豊富な経験を背景に、アクセシビリティとデザイン性の両立を実現します。ブランドイメージを保ちながら使いやすさを向上させたい企業に特に適しています。
株式会社デパート

株式会社デパートは、「Good Design, Good Experience」をミッションに掲げ、質の高いデザインと優れたユーザー体験の提供を通じて、より良い社会の実現に貢献することを目指しています。この理念に基づき、Webアクセシビリティをデザインとユーザー体験の根幹に関わる本質的な要素として捉え、その確保と向上に積極的に取り組んでいます。
特筆すべきは、自社サイト全体を対象として、WCAG2.2 の適合レベルAAに準拠することを目標として掲げ、試験結果をWebサイト上で公開している点です。同社が自ら高い基準を設け、達成度を透明性をもって示すことで、クライアントや社会に対する誠実な姿勢を表明していると言えるでしょう。
株式会社ディーゼロ

株式会社ディーゼロは「アクセシビリティをあたりまえに。」をスローガンに、Webアクセシビリティ専門家である平尾ゆうてん氏や専門チーム「サステナグロースチーム」により、デザインとアクセシビリティを融合させたサービスを提供しています。具体的には、多様なユーザーが直面する具体的な利用シーンを想定し、動画への字幕提供、音声コンテンツの文字起こし、色覚特性に配慮したカラーデザインなど、デザイン要素を調整しながらアクセシビリティを実現する実践的な対応策を提示しています。
また、大日本印刷株式会社および株式会社DNPコミュニケーションデザインと協業関係にあり、将来的には企業の経営課題解決にも貢献するような、より広範なソリューション提供を目指しています。
株式会社LYZON

株式会社LYZON(ライゾン)は、すべてのデザイナーがコーディングやフロントエンドのスキルも兼ね備えている点が大きな特徴です。そのため、Webサイトのデザイン段階からアクセシビリティを深く考慮した設計が可能となり、後工程での手戻りを減らし、最初からバリアフリーなデザインを目指すことができます。
大手企業への豊富な支援実績を持ち、大規模かつ複雑なWebサイトでもデザイン性を保ちながらアクセシビリティ要件を満たす高い技術力で企業のブランド価値を損なわない改善提案を行っています。また、「Webアクセシビリティ達成基準チェックリスト」を無償公開するなど、アクセシビリティの普及促進に貢献しています。
株式会社トルク

株式会社トルクは「デザインの力で情報格差をなくす」というミッションのもと、Webアクセシビリティをデザインとエンジニアリングにおける重要事項と位置づけています。
同社は、株式会社SmartHRの採用サイトなど、デザイン性の高さと高度なアクセシビリティ基準の達成を両立させた実績を数多く生み出しています。公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構が主催するWebグランプリの企業グランプリ部門「アクセシビリティ賞」で優秀賞を連続受賞するなど、外部からも取り組みが高く評価されています。
体制重視・トータルサポート型
このタイプの企業は、組織としてのアクセシビリティ対応を見据え、診断から改修、社内教育、運用体制の構築まで包括的なサービスを提供します。一時的な対応ではなく、継続してアクセシビリティを維持・向上させたい企業に適しています。
株式会社インフォ・クリエイツ

株式会社インフォ・クリエイツは「誰もが使えるWEBに 情報バリアフリーの実現を目指して」というビジョンのもと、Webアクセシビリティ検査、コンサルティング、研修、サイト制作、運用保守まで、アクセシビリティに関わるあらゆるフェーズを網羅したサービスを展開しています。
さらには、日本の主要企業のWebアクセシビリティ実装段階をAからEランクで評価した「Webアクセシビリティ指数 プログレスレポート」を定期的に公開し、企業が自社の対応レベルを業界標準と比較するための貴重なベンチマーク情報を提供しています。
SBテクノロジー株式会社

SBテクノロジー株式会社は、ソフトバンクグループの一員として、Webアクセシビリティ検査資格を保有する専門家が複数名在籍し、客観的基準に基づいた質の高いコンサルティングサービスを提供している点が特徴です。
同社は、アクセシビリティ対応を前提にした Web サイト構築や、アクセシブルなCMS(コンテンツ管理システム)導入支援を得意としています。花王株式会社が全700ものWebサイトのアクセシビリティ対応を進める際に、同社の「ウェブアクセシビリティ・コンサルティングサービス」を導入したことは、極めて大規模かつ複雑なアクセシビリティ対応プロジェクトにも対応できる組織力と専門性を有していることを示しています。
株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタルは、「顧客体験に革新をもたらすためにはクリエイティビティの発揮が欠かせない」という考えのもと、Webアクセシビリティの知⾒と広告会社ならではのクリエイティブな視点を融合させた課題解決アプローチを採っていることが特徴です。
企業の多様なニーズに対応するため、「診断」「ユーザビリティテスト」「改善支援」「大規模リニューアル支援」の4つの基本的なサービスメニューに加え、運用支援、ガイドライン作成、ワークショップなど多彩なオプションサービスを提供し、企業のフェーズに合わせた包括的なサポートを実現しています。また、電通グループの総合力を活かし、アクセシビリティ改善と同時に、ブランドマーケティング戦略、SEO対策、DX支援といった幅広い課題への対応も可能な点が強みです。
株式会社STYZ
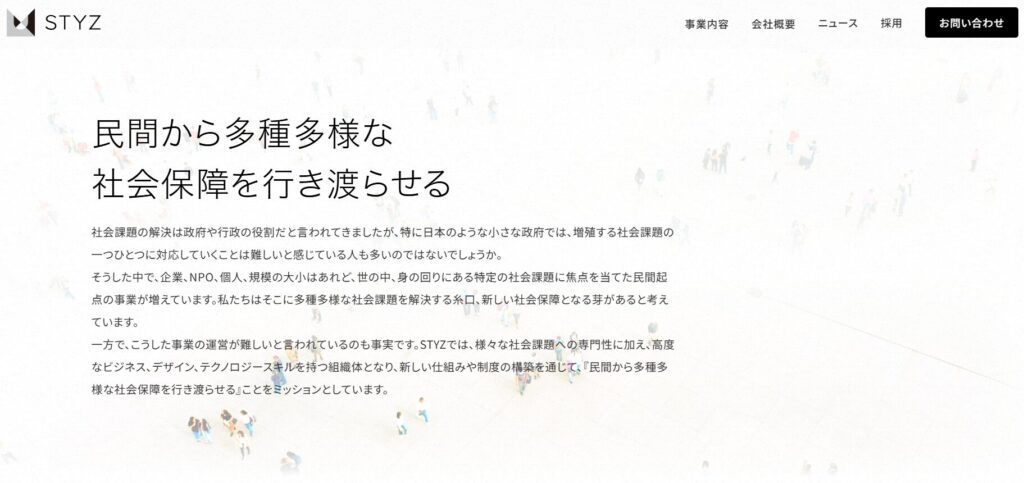
株式会社STYZ(スタイズ)が運営するインクルーシブデザイン専門スタジオ「CULUMU(クルム)」の最大の特徴は、高齢者、障がい者、外国人など、従来のデザインプロセスでは見過ごされがちだった多様な当事者との共創を重視している点です。
「CULUMUアクセシビリティ」サービスでは、アクセシビリティ専門家の知見と多様な障がい当事者のリアルな視点を組み合わせることで、Webサイトやアプリケーションのアクセシビリティ課題を可視化し、継続的な改善を支援しています。このサブスクリプション型のモデルは、アクセシビリティを一過性の対応ではなく、持続的な取り組みとして定着させることを目指す企業に適しています。
アクセシビリティ対応ウィジェットについて
アクセシビリティ対応を検討する中で、ウィジェット型の支援ツールについて情報収集されることもあるかと思います。専門的な支援との違いを理解するために、これらのツールの特性と注意点をご紹介します。
ウィジェットで実現できることと理解しておくべき限界
サイト自体を改修せずとも、一部の視覚支援機能をユーザーに提供できるようになります。 専用コードを埋め込むだけで導入が可能ですが、サイト自体の構造的な問題(HTMLマークアップの不備など)は解決されないため、導入しただけではアクセシビリティ基準に適合したとは言えません。
日本国内でも複数の企業がウィジェット型の支援ツールを提供していますので、次に代表的な企業をご紹介します。なお、これらは一時的な対応策として有効ですが、本格的な改善には支援企業への相談が重要だということを理解しておきましょう。
株式会社Kiva

株式会社Kivaが提供する「ユニウェブ」は、既存のWebサイトにHTMLタグを1行追加するだけで導入できる手軽さが特徴です。音声読み上げ、リンクの強調表示といった基本的なアクセシビリティ機能に加え、画像の代替テキスト(ALT属性)をAIが自動生成する先進的な機能を搭載しています。
アクセシレンズ株式会社

アクセシレンズ株式会社が提供する「アクセシレンズ」は、専用スクリプトを1行設置するだけで最短5分での導入が可能なクラウド型SaaSツールです。文字サイズの拡大・縮小、表示配色の変更といったアクセシビリティ支援機能を既存サイトに付加でき、専門的な知識がない担当者でも容易に導入できます。
ファシリティジャポン株式会社

ファシリティジャポン株式会社が提供する「FACIL’iti」(ファシリティ)は、Webサイト閲覧者自身が個々の困りごとに合わせて、Webサイトの表示をリアルタイムで最適化できる無料の閲覧支援ツールです。視覚特性から動作の困難さや認識特性まで、幅広い症状に対応した表示調整プロファイルを用意しています。
ファシリティジャポン株式会社が提供する「FACIL’iti」はこちら
よくある質問
アクセシビリティ支援企業への相談を検討する際によく寄せられる質問にお答えします。
制作会社があるが、他の企業に相談しても大丈夫?
全く問題ありません。アクセシビリティ対応は高度な専門性が求められる分野のため、専門企業に相談することをおすすめします。既存の制作会社とアクセシビリティ支援企業が協力して対応するケースも多く、それぞれの強みを活かした協業により、より効果的な改善が期待できます。
診断だけを依頼することはできる?
はい、多くの支援企業で診断のみのサービスを提供しています。まず現状を把握したい、改修の優先順位を決めたいという場合には、診断だけの依頼も十分有効です。診断結果をもとに、自社で対応するか、改修も含めて依頼するかを検討するとよいでしょう。
追加費用は発生する?
診断については、基本的に対象ページ数や検査項目によって料金が決まるため、事前に合意した範囲であれば追加費用が発生することは少ないです。ただし、診断後に改修を依頼する場合は、具体的な改修内容によって費用は変動します。透明性の高い料金体系を持つ企業を選ぶことが重要です。
どの企業に相談するか迷ったらどう選ぶ?
優先度や予算などが決まっていない場合は、まず実際の障がい当事者の方から自社サイトがどのように見えているかを知るところから始めることをおすすめします。実際に使う方の視点での評価を受けることで、改善の方向性や優先順位が明確になります。
どの支援企業を選ぶか社内で理解を得るには?
アクセシビリティはより多くのユーザーが利用しやすくなる取り組みであるため、ユーザー体験の向上や企業の社会的責任という観点から説明すると理解を得やすくなります。特に、実際の障がい当事者の方の体験談は社内の理解促進に効果的なので、当事者の声を重視する支援企業を選ぶとよいでしょう。
支援企業マップから最適なパートナーを見つけよう

本記事では、Webアクセシビリティ支援企業の選び方とおすすめ企業を紹介しました。
改めて整理する支援企業選択のポイント
- 自社の現状を把握する:対象サイトの規模や対応範囲を大まかに整理しておく(決まっていなければ、まず相談を)
- 支援タイプの特徴を理解する:それぞれの強みを把握し、自社が重視する点と相性が良さそうなタイプを見極める
- 実際の使いやすさを重視する:規格への適合も重要だが、それ以上に実際のユーザーにとっての使いやすさを大切にする
どのタイプの支援企業を選ぶにしても、まずは相談から始めることが何より重要です。多くの企業が無料相談を実施しており、自社の状況に応じた具体的で実践的なアドバイスを受けることができます。
今回紹介した情報を参考に、自社にとって適切な支援パートナーを見つけてみてください。
【無料ダウンロード特典】Webアクセシビリティ支援企業マップ2025
支援タイプ別に分類された支援企業を一覧化した「業界マップ(カオスマップ)」をご用意しました。本記事で紹介しきれなかった企業も掲載しており、支援企業の全体像を把握するのに役立つ資料です。パートナー選びの検討材料としてぜひご活用ください。