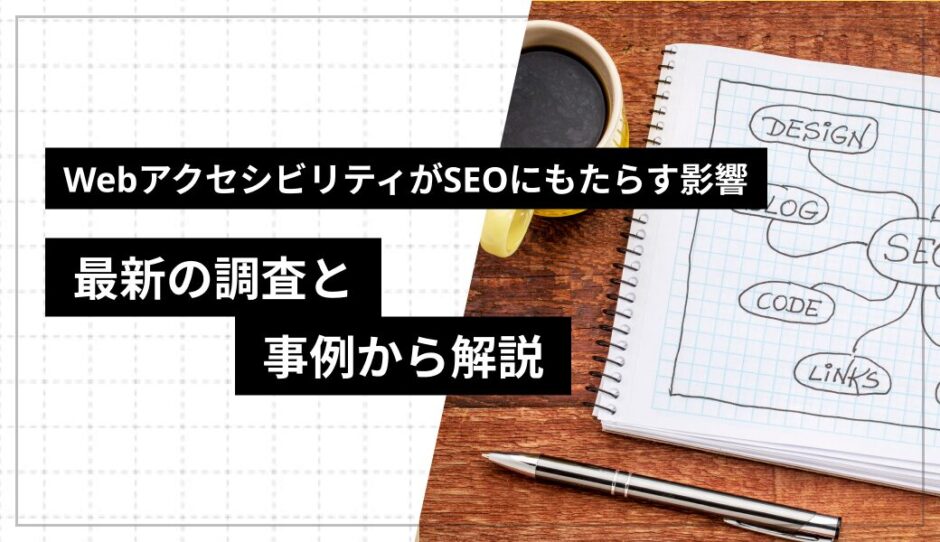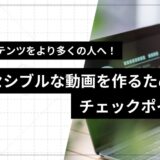近年、Webアクセシビリティの重要性が高まり続けています。 2024年4月には、日本においても改正障害者差別解消法が施行され、民間企業のアクセシビリティ対応が求められるようになりました。
しかし、多くの企業が抱える疑問として「アクセシビリティ対応はSEO(検索エンジン最適化)にどのような影響を与えるのか?」という点があります。実際のところ、Googleの検索アルゴリズムにおいてアクセシビリティは直接的にランキングには影響しないとされています。
では、なぜアクセシビリティ対応がSEOにも良い影響を与えるのでしょうか?本記事では、最新の調査データや企業の事例を交えながら、WebアクセシビリティとSEOの関係について詳しく解説します。
アクセシビリティは検索エンジンに評価されるのか?

GoogleのJohn Mueller氏は「アクセシビリティ対応自体が検索順位を直接上げることはない」と明言しています。(Google Search Central, 2022)
しかし、Googleはサイトの評価基準として「ユーザーエクスペリエンス(UX)」を重視しており、アクセシビリティはUXの一部として間接的にSEOに影響を与える可能性があります。
特に、以下のような要素はSEOにも影響を与える重要なポイントです。
- 見出しの適切な使用(H1~H6タグの論理的な構造)
- alt属性の適用(画像の説明テキストを適切に設定)
- HTMLの適切なマークアップ(スクリーンリーダーだけでなく、検索エンジンの理解にも貢献)
- サイトの可読性の向上(フォントサイズやコントラストの最適化)
実際、Googleの公式ガイドラインでも「アクセシビリティとSEOは目的こそ異なるが、サイトの品質向上という点で共通している」と述べられています。
アクセシビリティ対応がSEOに与える具体的な影響

アクセシビリティの向上は、ユーザー体験(UX)の改善に直結し、結果的にSEOの評価向上にもつながると考えられます。
例えば、適切な見出し構造を設計することで、検索エンジンはページの情報を正しく理解しやすくなります。また、alt属性を適切に設定すれば、画像検索からの流入が増加します。さらに、Webサイトの可読性が向上すれば、直帰率が低下し、滞在時間が増えるなど、SEOにポジティブな影響を与える指標が改善されることが分かっています。
以下では、具体的なSEOへの影響について詳しく解説します。
見出し構造の適切な設定は検索結果の可視性を向上させる
アクセシビリティ向上の基本である「論理的な見出し階層」「適切なHTML構造」は、そのまま検索エンジンに対するコンテンツの分かりやすさ向上につながります
例えばH1~H2タグでページの階層構造を正しくマークアップすれば、Googleもページ内の重要トピックを把握しやすくなります。これは結果として適切なキーワードの評価や、特定クエリに対するページ内該当セクションの抽出(Passage Indexing)などにも寄与します。また構造が明確だと検索結果にサイトリンクやジャンプリンクが表示される可能性も高まります。アクセシビリティの観点から見出しやリストで文章構造をマークアップすることは推奨されていますが、これらはSEO内部対策としても有効であり、双方にメリットがあります
実際、国内のWeb制作会社の解説でも「アクセシビリティ対応はユーザーへ、SEO対策は検索エンジンへ情報を分かりやすく伝えるという共通点があり、両方に真摯に取り組むことでコンテンツ品質が向上する」と述べられています。
参照:https://giginc.co.jp/blog/giglab/accessibility-mandatory
つまり、サイト構造の読みやすさを高めることは検索エンジンにとっても有益で、結果的に検索評価の向上(=SEO効果)につながり得るのです。
代替テキスト(alt属性)や適切なマークアップの効果
画像に付与するalt属性(代替テキスト)はアクセシビリティとSEO双方にとって重要です。アクセシビリティの面では視覚障害のあるユーザーへの説明となり、SEOの面では検索エンジンが画像内容を理解しテキストとして評価する材料になります。Googleは画像検索のアルゴリズムでaltテキストを重視しており、altに含まれるキーワードや説明は画像検索結果の関連性判断やキャプション表示に利用されます。また一般のWeb検索でも、altテキストはページのHTML上のテキストとしてクロールされるため、コンテンツの補足情報となります
適切で情報豊富なaltを付けることで、画像に依存していた情報が検索エンジンにも伝わり、結果としてページ全体の評価向上やロングテールキーワードでの露出増加が期待できます。反対にalt属性が欠如していると、スクリーンリーダー利用者に内容が伝わらないだけでなく検索エンジンにも画像の意味が伝わらず機会損失になります
加えて、HTML5のセマンティックタグ(<header>や<nav>、<main>、<footer>等)を正しく使うこともアクセシビリティとSEOの両面でプラスになります。スクリーンリーダーはこれらタグでページ領域を認識しやすくなり、検索エンジンも主要コンテンツ部分(<main>)やナビゲーション部分を区別しやすくなります。例えば記事本文とサイト全体のヘッダー・フッターを明確に分けてマークアップすれば、検索エンジンは主要な本文コンテンツにフォーカスしやすくなり、不要なナビゲーションテキストとの混同を減らせます。これも間接的にですがクローラビリティやコンテントの評価精度向上につながります。
ユーザーエクスペリエンス(UX)向上がもたらす間接的SEO効果

アクセシビリティ改善の多くはユーザーエクスペリエンスの向上を伴います。例えば文字サイズの拡大・色コントラストの改善は高齢者や弱視のユーザーだけでなく一般ユーザーにも読みやすさを提供し、結果としてサイト滞在時間の延長や直帰率の低下につながる可能性があります
ウェブアクセシビリティの専門機関BOIAも「アクセシブルなサイトはユーザーのエンゲージメントを高め、結果として直帰率を下げる」と報告しています
直帰率が改善すれば、ユーザーが検索結果にすぐ戻ってしまう“ポゴスティッキング”の減少が期待でき、これは検索エンジンから見たコンテンツ満足度の間接的なシグナルになり得ます。
また、サイトが使いやすく情報が探しやすいほどコンバージョン率が上がるケースも多く報告されています。アクセシビリティ対応によってフォーム入力がしやすくなったり(ラベルの明示やエラーメッセージの改善)、ページ遷移がスムーズになることで問い合わせ・購入といったアクションが増加すれば、ビジネス成果が向上します。その結果、ユーザーからの評価が高まり被リンクや口コミが増えるといった好循環が生まれる可能性があります。
実際、アクセシビリティに注力する企業は売上面でも恩恵を受けているとの調査もあります。アクセンチュアの研究では「アクセシビリティ対応を優先する企業は4年間で平均28%の収益増加を達成した」との結果が出ており使いやすさが顧客増・売上増につながることが示唆されています。このようにユーザー体験の向上(UX改善)はユーザーのサイト評価や行動指標にポジティブな変化をもたらし、直接ではないにせよSEOに間接的な良影響を及ぼすと考えられます。
その他の具体的な効果例
アクセシビリティ対応には他にも検索エンジンへのポジティブな副次効果がいくつかあります。
例えばページに言語属性(lang)を適切に指定することは、多言語サイトでの検索結果表示の適切化(正しい言語でインデックスされる)に役立ちます。またマウス無しでも操作できる設計(キーボードでのフォーカス移動が可能など)は、検索クローラがリンクをたどる際にも妨げが少ない構造と言えます。(例えばJavaScriptでカスタム実装されたリンクより、生のHTMLリンクの方がクローラに認識されやすい)。ポップアップやインタースティシャルを控えるのもアクセシビリティ上望ましいですが、これはページエクスペリエンスの指標にもなっており(煩わしいインタースティシャルの非表示がランキング指標の一つ)、SEOに直接プラスです。
さらに、アクセシビリティ対応でモバイル環境への適応性が高まる点も見逃せません。レスポンシブデザインやテキスト拡大対応はモバイルユーザビリティを向上させ、Googleのモバイルフレンドリー評価で高得点を得やすくなります。以上のように、アクセシビリティの個別施策(代替テキスト、見出し構造、適切なタグ付け、言語指定、モバイル対応強化など)は、そのままSEO内部対策の好事例と重なる部分が多く、結果として検索エンジン最適化にも寄与するのです。
アクセシビリティ改善がSEOに与えた具体的な事例とデータ

海外事例:アクセシビリティ対応でトラフィックが平均12%増加
最大級のSEOツール企業であるSemrushは2022年に約847のWebサイトを対象とした大規模調査を行い、アクセシビリティ改善がトラフィックに与える影響を分析しました。
この調査では、障害者対応のアクセシビリティソリューション導入(アクセシビリティ修正)を行ったサイト群について、実施後3か月で平均12%も全体トラフィックが増加したことが報告されています。参照:accessibe.co
さらに注目すべきは、約73.4%ものサイトでオーガニック(自然検索)トラフィックが増加した点で、アクセシビリティ改善によって大半のサイトで検索流入がプラスに転じたことを示しています。増加幅についても、約66.1%のサイトが最大で50%以内の自然検索流入増加を達成し、中には検索流入が1.5倍以上に伸びた例もあったとのことです
この結果は「アクセシビリティとSEOは表裏一体であり、アクセシビリティ対応がオーガニック成長に寄与する」ことを裏付けるものとして業界で注目されました。
国内事例:アクセシビリティ改善で検索インプレッションが556%に増加
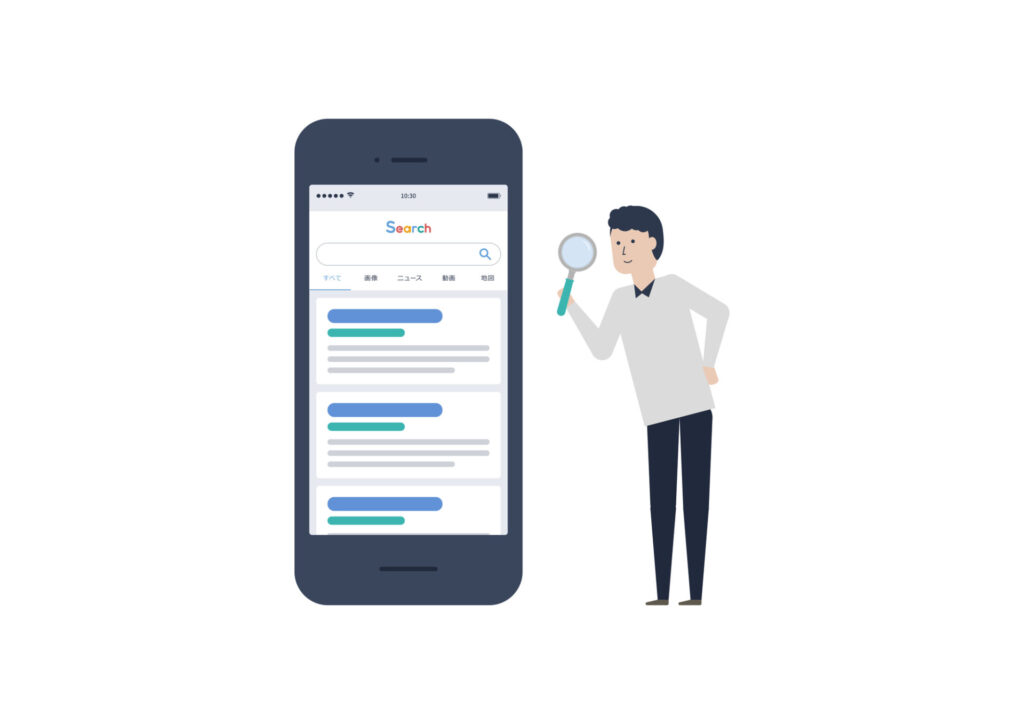
日本企業のケーススタディとして、Web制作会社ネモフィラが自社コーポレートサイトで行った検証が参考になります。ネモフィラ社は2023年に自社サイトをWCAG 2.1のAAレベルに準拠するよう改善し、その前後でGoogle検索の表示回数(インプレッション数)がどう変化したかを分析しました。参照:positips.info
その結果、自然検索におけるサイトの表示回数は2023年8月時点の4,607回から、改善後の2024年4月には25,620回へと飛躍的に増加しました。これは約556%増(5.5倍超)という驚異的な伸びであり「アクセシビリティ対応がSEOに繋がることを裏付ける結果」と報告されています
同社はアクセシビリティだけでなくコンテンツ拡充等も並行して行っていたものの、明らかにアクセシビリティスコアの向上と歩調を合わせて検索インプレッションが右肩上がりになった点が注目されます。
特に見出し構造の整備やaltテキスト充実など、前述したアクセシビリティとSEOの重なる施策を実施したことでサイト全体の品質スコアが上がり、検索エンジンからの評価が向上したと推測できます。同社は「ウェブアクセシビリティへの取り組みは一石二鳥(=アクセシビリティ対応がそのままSEO対策になる)」と結論付けており今後もアクセシビリティを強化していく方針を示しています。
その他の事例・データ
具体的な数値を伴う事例はまだ限られますが、他にもアクセシビリティ改善とSEO効果の関連を示す報告が増えています。例えば、イギリスの公共機関サイトではアクセシビリティ強化後にサイト訪問者が増加し、直帰率が低下したケース(sitecore.com)や、米国大手小売の事例で商品検索経由の流入とコンバージョンが向上した例があると伝えられています。
また、日本でもアクセシビリティに早期から取り組んでいる一部企業(例えば楽天グループやトヨタ自動車のサイトなど)は、ユーザビリティとSEO双方で高い評価を得ています。これらは定量的な公開データこそ少ないものの、「サイトを誰にとっても使いやすくした結果として検索評価も向上する」という共通の傾向を裏付けています。
さらに、検索結果でのクリック率(CTR)への影響について明示的なデータは多くありませんが、アクセシビリティ改善がCTRを高める可能性も指摘されています。例えば構造化データマークアップや適切なタイトル・ディスクリプション設計(これらも広義ではアクセシビリティの一環です)は、検索結果での見栄えや理解度を上げ、ユーザーがクリックしたくなる結果スニペットを生成します。その結果CTR向上につながれば、間接的にランキング改善に寄与することも考えられます(※CTR自体は直接のランキング要因ではないとGoogleは述べていますが、関連性の高い結果はクリックされる傾向があり、それをアルゴリズムが学習する可能性があります)。
以上のように、具体的事例からもアクセシビリティ対応が検索トラフィックやユーザー指標を改善し、それがSEO成果(オーガニック流入増、エンゲージメント向上など)につながった例が報告されています。特に直近2~3年で、アクセシビリティとSEO双方に取り組む企業が増え、その効果検証が進んできています。
2024年以降、アクセシビリティ重視の流れが加速
2024年は日本においてWebアクセシビリティ対応が大きな節目を迎える年です。2024年4月1日施行の改正障害者差別解消法により、これまで努力義務とされてきた民間事業者のウェブアクセシビリティ対応が一部義務化される見込みで(合理的配慮の提供義務化)、企業ウェブサイトでもアクセシビリティ確保が重要な法的要件となりつつあります。
これを受けて国内企業の間でアクセシビリティへの関心が急速に高まっており、特に大手企業や公共機関を中心にサイト改修の動きが出ています。ウェブ担当者向けの情報サイトやセミナーでも「今、企業に求められるアクセシビリティ対応」「2024年義務化とSEOへの影響」といったテーマが取り上げられ、アクセシビリティ=社会的責任であると同時に競争力強化策という認識が広まりつつあります。例えばWeb担当者Forumの連載でも「アクセシビリティ改善で平均12%トラフィック増加」というデータが紹介されるなど(suzukikenichi.com)、SEOの文脈でアクセシビリティが語られる機会が増えました。
今後、ユーザーの誰もが使いやすいサイト作りが当たり前の水準になるにつれ、アクセシビリティ未対応のサイトは相対的にユーザー評価も検索評価も下がっていく可能性があります。言い換えれば、2024年以降はアクセシビリティ対応が「差別化要因」から「当たり前の前提条件」へと移行し、それを満たさないサイトは信頼性やユーザビリティの面で不利となっていくと予測されます。これは検索エンジンにとっても好ましいWeb全体の方向性であり、長期的には検索アルゴリズムにも何らかの形で反映されるかもしれません。