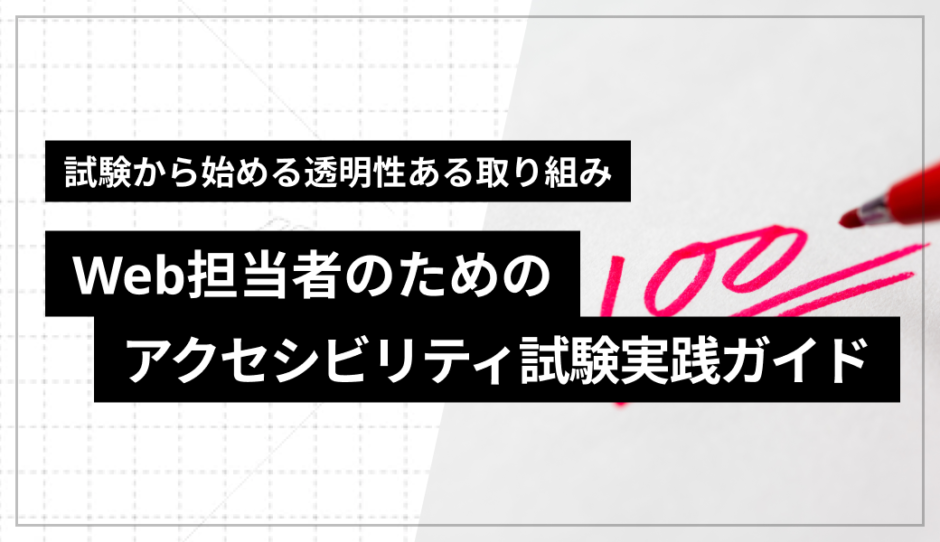Webアクセシビリティ試験は、自社サイトが多様なユーザーにとって使いやすいかを確認するだけでなく、法的・社会的要請への対応としても重要です。特に日本国内の公的機関では、WCAG 2.0を基に策定されたJIS X 8341-3:2016に基づく試験の実施と適合レベルの表明が推奨されており、適合表明の種類によっては試験結果の公開も求められます。公的機関だけでなく一般企業においても、コンプライアンス対応や信頼性向上の観点から、アクセシビリティ試験の実施と情報開示の重要性が高まっています。
本記事では、初めてWebアクセシビリティ試験を実施する担当者向けに、試験の種類や選び方、効果的な実施手順、結果の公表についてまで、実践的なガイドを提供します。
なお、日本企業の多くがJIS規格に基づく試験と適合表明を行う一方で、グローバル展開を行う企業などはWCAG 2.1に基づいた評価を実施することもあります。本記事では主にJIS X 8341-3:2016に基づく試験手法を解説しますが、基本的なアプローチは他の規格にも応用可能です。
Webアクセシビリティ試験の種類と選び方
まず知っておくべきポイントとして、Webアクセシビリティ試験は特定の専門機関や認証団体が実施しなければならないという決まりはありません。日本国内では一般的に、JIS X 8341-3:2016の達成基準を正しく理解し、適切に評価できる知識を持つ者であれば、企業の担当者自身、自治体職員、外部の専門会社など、誰でも実施することができます。
試験の種類
アクセシビリティ試験には主に3つの種類があります。
自動検査(ツールを用いた試験)
自動検査ツールを使用して機械的にチェックする方法です。例えば「miChecker」「WAVE」「axe」などのツールを使えば、HTMLコードの問題点やコントラスト不足などを自動的に検出できます。
手動検査(専門家による評価)
アクセシビリティの専門知識を持つ人が、ガイドラインに基づいて詳細に評価する方法です。キーボードだけでのナビゲーション確認や、音声入力での操作性の検証など、人間の判断が必要な項目を網羅的に評価します。
ユーザーテスト(当事者による検証)
高齢の方や障がいのあるユーザーに実際にサイトを利用してもらい、問題点を確認する方法です。視覚障がい者にスクリーンリーダーでの操作性を確認してもらったり、運動障がいのある方に入力操作の使いやすさを評価してもらうことで、実際の利用環境での課題が明らかになります。
試験方法の比較
以下の表で3種類の試験方法を比較してみましょう。
| 試験方法 | メリット | デメリット | 適している場面 |
|---|---|---|---|
| 自動検査 | ・多数のページを効率的に検査可能 ・コストが比較的低い ・一貫した基準で評価可能 | ・全体の約20~30%の問題しか発見できない ・コンテキストに基づく判断ができない | ・初期スクリーニング ・大規模サイトの概要把握 |
| 手動検査 | ・自動検査では発見できない問題も検出可能 ・コンテキストに応じた判断ができる | ・専門的な知識が必要 ・時間とコストがかかる ・人による判断のため一貫性に課題 | ・重要ページの詳細評価 ・複雑なインタラクションの検証 |
| ユーザーテスト | ・実際のユーザーが直面する問題を直接把握 ・使いやすさの実践的な評価が可能 | ・参加者の募集などに時間とコストがかかる ・個人の経験やスキルに依存する | ・主要機能の実用性確認 ・ユーザー体験の向上 |
自動検査ツールのみでは全ての問題を発見できないため、人による手動検査を組み合わせることが推奨されています。限られたリソースでは、まず自動検査で基本的な問題を発見し、重要なページには手動検査を追加するという段階的アプローチが効果的です。
試験の実施手順

Webアクセシビリティ試験は、対象ページの選定から始まり、適合レベルの設定、実際の検査実施、結果の集計という流れで進めます。まずは試験の基本的な手順を理解しましょう。
試験対象の決定
「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」では、試験対象の決定方法として以下の2つのアプローチが示されています。
Webページ単位での試験
特定のページのみを対象とする試験方法です。この場合、試験結果はそのページのみに適用され、「このページはJIS X 8341-3:2016のレベルAに準拠しています」といった表明ができます。
Webページ一式単位での試験
Webサイト全体を対象とする試験方法です。この場合、以下の4つの方法から選択して試験対象ページを決定します。
- 全てのページを選択する方法:100ページ程度までの小規模サイトに適した方法。サイト全体の準拠を確実に保証できる。
- ランダムに選択する方法:サイト規模に関わらず40ページ程度が目安となる。客観性のある試験が可能だが、恣意的な選択は無効となるため注意が必要。
- 代表的なページを選択する方法:トップページ、問い合わせページなど利用頻度の高いページを選定。利用者視点で重要なページを確実に確認できる。
- 代表的なページとランダムに選択したページを併用する方法:100ページ以上の中・大規模サイトに推奨。目安としては、代表的なページとランダム選択のページ、両方を合わせて合計40~50ページ程度を対象にするとよい。
適合レベルの設定
試験前には、どの適合レベル(A、AA、AAA)の達成を目指すかを決定する必要があります。適合レベルは試験結果の公表時に明示する必要があるため、事前に決定しておきましょう。
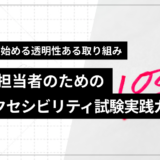 試験から始める透明性ある取り組み – Web担当者のためのアクセシビリティ試験実践ガイド
試験から始める透明性ある取り組み – Web担当者のためのアクセシビリティ試験実践ガイド
試験の実施タイミング
重要なポイントとして、サイト完成直前に試験を行うのでは遅いということを理解しておきましょう。リリース直前ですぐには改修できない問題が見つかると、リリース延期やアクセシビリティが不完全な状態での公開を余儀なくされることがあります。そのため、情報設計段階・デザインテンプレート完成時・開発途中の結合テスト時などのタイミングで、段階的に試験を行うことが推奨されます。開発の早い段階から試験を組み込むことで、後戻り作業を最小限に抑え、効率的にアクセシビリティを向上させることができます。
具体的な実施手順とチェックリストの活用
次に、アクセシビリティ試験の具体的な手順を説明します。WAIC(ウェブアクセシビリティ基盤委員会)の提供するチェックリストを活用すれば、効率的かつ漏れのない検証が可能になります。
- 準備段階:
- 「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」より、実装チェックリストを入手(または独自のチェックリストを用意)
- テスト対象ページの一覧を作成
- 検査環境(ブラウザ、自動検査ツール、支援技術など)を整える
- 自動検査の実施:
- 選定したツールで対象ページを検査
- 機械的に検出できる問題(代替テキスト漏れ、色のコントラスト不足など)を特定
- 検出結果を実装チェックリストの該当項目に反映
- 手動検査の実施:
- 手動検査が必要なページ(トップページや重要な機能を持つページなど)を選定
- 実装チェックリストに沿って選定したページを検証
- 自動検査では発見できない問題(見出し構造の適切さ、フォーム操作性など)を特定
- 検証結果を実装チェックリストの該当項目に反映
- ユーザーテスト(可能な場合):
- 障がい者などテスト参加者を募集し、実際にサイトで操作してもらう
- 実際の利用環境での問題点(使いにくさ、理解しづらさなど)を特定
- 発見された問題を実装チェックリストの該当項目に反映
- 結果のまとめ:
- 実装チェックリストの結果をもとに、達成基準チェックリストを作成
- 各達成基準の適合状況を評価し、試験対象の対応度を判定
- 問題の重要度に基づいて改善計画を策定
試験結果は各達成基準について「適合」「不適合」「非適用」と評価され、これに基づいて試験対象(ページ単位またはサイト一式単位)の対応度が決まります。対応度は、選択した適合レベル(A、AA、AAA)の全ての達成基準を満たしている場合は「準拠」、一部の達成基準を満たしていない場合は「一部準拠」となります。
試験結果の公表と適合表明

試験が完了し結果が整理できたら、次のステップとして結果の公表とアクセシビリティへの取り組みの表明を検討します。この表明は「適合表明」という形で行われることが多く、透明性確保と社会的責任の観点から重要な意味を持ちます。
WAICの「対応度表記ガイドライン」によれば、「準拠」を表記する場合はアクセシビリティ方針と試験結果の公開が必須です。「一部準拠」の場合は方針の公開は必須ですが、試験結果の公開は任意とされています。民間企業にとって試験結果の公表に法的義務はありませんが、積極的な情報開示はユーザーからの信頼獲得につながります。
試験結果の公表と適合表明の形式
試験結果の公表と適合表明は通常、Webサイト内の「アクセシビリティ方針」ページで行われます。方針ページでは主に以下の要素が組み合わされて公開されます。
1. アクセシビリティ方針
組織のアクセシビリティに対する基本姿勢や取り組み方針を示すもので、対応するガイドラインや目標とする適合レベルなどを記載します。
2. 適合表明
特定の適合レベル(A、AA、AAA)への準拠状況を表明するもので、表明日、準拠しているガイドライン名と適合レベル、対象範囲、除外コンテンツの説明などを含みます。
3. 試験結果
実施した試験の結果を公表するもので、多くの組織では対応状況の概要のみを簡潔に記載します。より詳細な試験結果(試験日、対象ページ、各達成基準の適合状況など)は必ずしも公表する必要はなく、組織内での改善活動のための内部資料として活用されることも一般的です。公的機関では詳細な試験結果の公表が推奨されますが、民間企業では概要のみの公表が主流です。
全面的な適合が難しい場合でも、「段階的な対応」や「特定ページの適合」など現実的な範囲での公表が、透明性と誠実さを示す上で重要です。また、これらの情報は定期的に更新することが望ましいとされています。
試験を活かして透明性のある取り組みを
Webアクセシビリティの向上は一度の試験で完結するものではなく、継続的な改善プロセスとして取り組むことが重要です。大規模リニューアル前後、新機能追加時、定期的な見直し(年1〜2回程度)など、適切なタイミングで試験を実施しましょう。
試験結果は単なる評価にとどめず、適合表明とともに公表することで、組織のアクセシビリティへの姿勢を示すコミュニケーションツールとなります。対応度が「準拠」か「一部準拠」かよりも、現状を正確に把握し公開した上で継続的に改善していく姿勢こそが、真のアクセシビリティ向上につながるということを忘れないようにしましょう。