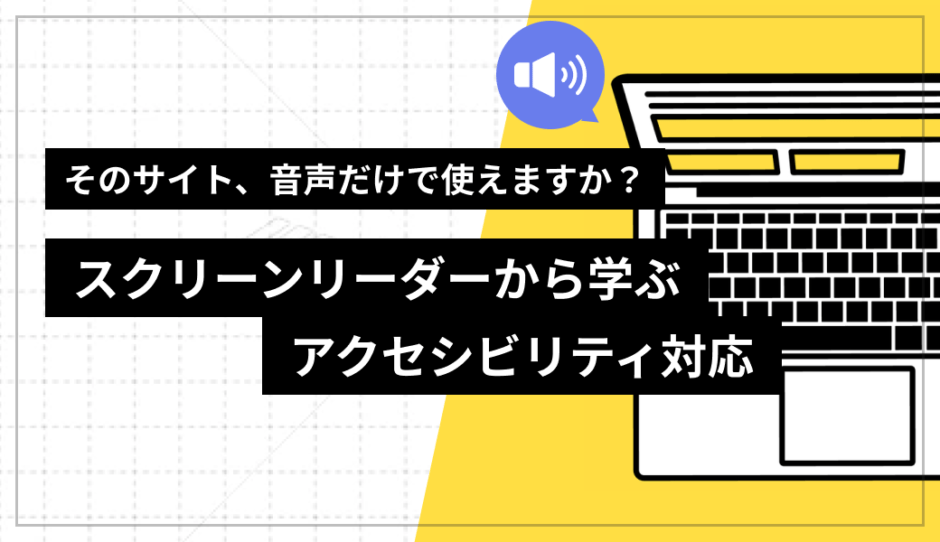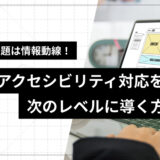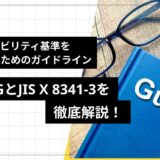Webサイトを利用する時、多くの方は画面を見ながら情報を得ますが、視覚に障がいのある方々は、画面を見ることができない、あるいは見えづらい状態でWebサイトを利用しています。そのため、画面の情報を音声で読み上げる「スクリーンリーダー」という支援技術が不可欠となっています。また、この技術は、視覚障がいのある方だけでなく、様々な理由で画面を見ることが難しい方々にも活用されています。
しかし、適切な対応がされていないWebサイトでは、スクリーンリーダーを使用しても必要な情報を得ることすら難しい状況が発生しています。音声だけでの利用を考慮していないサイトが依然として多く存在するのです。この記事では、スクリーンリーダーユーザーが直面する具体的な困難と改善方法から、より多くの人が利用できるWebサイトづくりのヒントをご紹介します。
スクリーンリーダーが頼りの方たち
日本の視覚障がい者数は約164万人と推計されています。特に、全盲の方や重度の弱視の方にとって、スクリーンリーダーは情報アクセスの生命線となっています。銀行での取引、買い物、行政サービスの利用など、現代社会では多くの重要なサービスがWebを通じて提供されているため、スクリーンリーダーは日常生活に不可欠なツールとなっているのです。
さらに、音声による情報アクセスは、視覚障がいのある方だけの課題ではありません。加齢による視力の低下、事故や病気による一時的な視力障がいなど、誰もが「画面が見えない」「画面が見づらい」状況に直面する可能性があるのです。
では、スクリーンリーダーを使用する方々は、実際にどのようにWebサイトを閲覧しているのでしょうか?
スクリーンリーダーとは?

スクリーンリーダーは、画面に表示される情報を音声で読み上げるソフトウェアです。Windows PCならNVDA(無料)、MacならVoiceOver(標準搭載)といった選択肢があります。スマートフォンでも同様の機能が標準で搭載されており、iPhoneではVoiceOver、AndroidではTalkBackと呼ばれています。
PCでスクリーンリーダーを利用する際は、キーボードの矢印キーやTabキーで画面上を移動すると、スクリーンリーダーが各要素を順番に読み上げていきます。例えば、「見出しレベル2 新着情報」「リンク お問い合わせ」「編集可能 メールアドレス入力欄」といった形で情報が読み上げられます。利用者は音声を聞きながら、必要な情報を探したり、リンクを選択したり、フォームに情報を入力したりします。
スマートフォンでは、画面を指でタップやスワイプすることで操作を行います。指で触れた場所の情報が読み上げられ、ダブルタップで選択やリンクの実行ができます。画面の視認性に頼ることなく、必要な操作が可能となっています。
スクリーンリーダーは、Webページの構造を解析して情報を読み上げるため、適切なHTML構造や属性の設定が不可欠です。例えば、画像に説明文が設定されていない場合は「画像」とだけ読み上げられ、内容を把握することができません。このような困難が生じる場面について、次のセクションでより詳しく見ていきましょう。
ユーザーが直面している困難と改善方法
スクリーンリーダーユーザーがWebサイトを利用する際、様々な場面で情報へのアクセスが阻まれています。一見問題なく見えるWebサイトでも、音声での読み上げを前提とすると、多くの困難が浮かび上がってくるのです。以下に、代表的な問題点と解決策をご紹介します。
フォーム入力において直面する困難
フォームの入力欄に適切なラベル設定がされていないと、スクリーンリーダーがどの欄が何を入力する場所なのかを正しく読み上げることができません。また、視覚的には「※」マークで必須項目を示していても、そのマークがテキストとして設定されていないと、必須か任意かの判断もできません。EC サイトで住所や電話番号といった情報が入力できないと、商品の注文を完了させることができない事態となります。
改善方法
以下の対応により、フォーム入力の操作性が大きく向上します。
- 各入力欄に何を入力する場所かを明示
- 必須項目かどうかを明確に指定
- エラーの内容を具体的に表示
画像認識において直面する困難
画像やボタンに代替テキスト(alt属性)が設定されていない、もしくは不適切な説明文が設定されていると、スクリーンリーダーが画像の内容を正しく伝えることができません。商品写真を例にすると、商品の特徴や他の商品との違いが判断できず、目的の商品を選ぶことができなくなってしまいます。
改善方法
画像の目的や性質に応じて、適切な代替テキストを設定することが必要です。
- 商品画像には具体的な特徴を記述
- 装飾用の画像は読み上げ不要と指定
- ボタンやリンクの画像には機能を説明
ページ構造把握において直面する困難
見出しタグ(h1~h6)が適切に使用されていない、もしくは装飾目的でのみ使用されていると、Webページの論理的な構造をスクリーンリーダーが解釈できません。その結果、長文のお知らせページなどで、目的の情報にたどり着くまでページの先頭から最後まで読み上げなければならず、効率的な情報取得ができなくなります。
改善方法
論理的なページ構造を実現するため、以下の点に注意して実装します。
- ページの重要度に応じて見出しを設定
- 関連する情報のまとまりを適切に区分
- コンテンツの主従関係を明確に設定
これらの問題点への対応は、実は他にも大きな可能性を秘めています。次のセクションでは、スクリーンリーダーへの対応がもたらすビジネス面でのメリットについてご紹介します。
スクリーンリーダー対応で広がるビジネスチャンス
スクリーンリーダーユーザーへの配慮は、実は企業にとっても大きなメリットをもたらします。
検索エンジン最適化(SEO)の向上
スクリーンリーダーとWeb検索エンジンは、共通の要素を読み取って解析しています。そのため、スクリーンリーダー対応を進めることは、自然と検索結果での表示順位向上にもつながるのです。
ユーザー層の拡大
音声での情報提供に対応することで、高齢者や一時的な障がいがある方など、潜在的なユーザー層へのアプローチが可能になります。また、まぶしい環境や暗い場所など、画面が見づらい状況での利用者にとっても使いやすいサイトとなるため、アクセス数の増加も期待できます。
ブランド価値の向上
誰もが使いやすいサイトを提供することは、企業の社会的責任(CSR)の実践となります。こうした取り組みは、企業イメージの向上にもつながり、長期的な企業価値の向上に寄与します。
こうした点から、スクリーンリーダーユーザーに配慮したWebサイトづくりは、企業の成長とユーザー体験の向上を同時に実現する重要な取り組みといえるでしょう。
始めよう、スクリーンリーダー対応
スクリーンリーダーは、視覚に頼らずにWebサイトを利用するための重要な技術です。そして、「見えない」状況は誰にでも起こりうる現実でもあります。「見えない」場合を想定して適切な対応を行えば、より多くの利用者が必要な情報にアクセスし、スムーズな操作を行えるようになるのです。
まずは自社のサイトの状態をスクリーンリーダーユーザーの視点で確認してみませんか?MacならCommand + F5、WindowsならNVDAをインストールすることで、すぐにスクリーンリーダーを体験できます。自社のWebサイトのトップページを開いて、Tabキーを押しながら移動してみてください。
より詳しく知りたい方には、私たちの無料Webアクセシビリティ診断もお勧めです。実際に視覚や聴覚に障がいをお持ちの方々がWebサイトを確認し、リアルな利用者視点からのフィードバックを提供しています。
スクリーンリーダーへの対応に、特別な技術は必要ありません。基本的な実装の工夫だけで改善できる部分が多くあります。ぜひスクリーンリーダーユーザーの立場で考えることから始め、どんな利用者にとっても使いやすく、わかりやすいWebサイトを目指していきましょう。